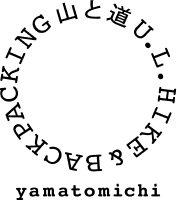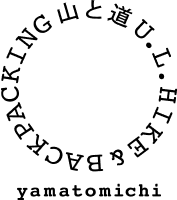#2 冷めたチキンとサボテンだらけの砂漠とピザ屋での大騒ぎ
#2 冷めたチキンとサボテンだらけの砂漠とピザ屋での大騒ぎ
アメリカの3大トレイルを制覇したトリプルクラウン・ハイカーであり、この山と道JOURNALSでもコンチネンタルディバイドトレイルやアパラチアントレイルでのスルーハイク記を連載してくれたトレイルネーム「スケッチ」こと河戸良佑さんのアリゾナトレイルでのスルーハイク記、全3回の#2です。
メキシコ国境からユタ州との州境まで、南北800マイル(約1,280km)に渡って伸びるアリゾナトレイルを52日間かけて歩くスケッチ。ともあれ、歩いているよりもパーティで飲んだくれたり、ホテルでウダウダしたりしているエピソードが多めなのはこれまで通りですが。今回も冷めたチキンに齧り付き、バーをハシゴし、ピザ屋で大騒ぎしつつサボテンだらけの砂漠を進みます。
どうぞスケッチの旅に今回もお付き合いください!
36歳になったあと
僕はアリゾナ州南部のトゥーソン郊外にある安モーテルのベッドに横になりながら、左手にビール缶を持ち、右手でサイドテーブルに置かれたフライドチキンの山からひとつつまみ、無感情にむしゃむしゃと食べた。たちまち口の中が安っぽい油で覆れ、それを洗い流すかのようにビールをごくごくと飲んだ。

アメリカのスーパーでは驚くほど安くフライドチキンが購入できる。体には良くなさそうだが、必ず買ってしまう。
ベッドの向かいの壁に掛けられた大型テレビには『スターウォーズ』の長ったらしいオープニングスクロールが映し出されていた。ケーブルテレビのこのチャンネルでは『スターウォーズ』の映画を順に放送しているようで、これが実に5作目の放送である。

アリゾナトレイル自体は平坦で比較的ラクだが、日陰がないので太陽の日差しが容赦なく降り注ぐ。
アリゾナトレイルをスタートして7日目。メキシコ国境から118マイル(189km)歩いてきた。まだ旅は序盤であるのに、僕は心底疲れ切っていた。2年ぶりのロングディスタンスハイキングだし、それに加えて脳天を焦がすような砂漠の日差しだ。さらに自身でも意外であったのが、先日36歳になり、歳を重ねたことによる精神的な疲労を感じていた。そのどれもが僕を怠惰な3日連続のゼロデイ(全く歩かない日)へと誘っていた。
アリゾナトレイルは全長が800マイル(1200km)。中距離のロングディスタンストレイルと言ったら変な響きだが、過去に歩いてきたそれぞれ4000kmを超えるパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)、コンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)、アパラチアントレイル(AT)と比べるとかなり短い。故に先の3本のようにスノーシーズンの到来までに踏破しなくてはならないといったデッドラインが存在しないため、それほど急ぐ必要がないのだ。加えて僕には帰国しても待つ人がいるわけでもなく、やるべき仕事があるわけでもない。だからアメリカでダラダラと過ごす方が気楽だった。

寒くないので朝ものんびりとテントで過ごすことができる。
もう1本のフライドチキンに手を伸ばそうとした時、モーテルのドアをノックする音がした。もう3日も部屋にこもってダラダラしているのでいいかげんハウスキーピングが来たのかと思いドアを開ける。だが、そこにいたのはハイカーフレンドのマタドールだった。
「一体どうしたんだい?」
「おい、メッセージ見てないのか? 俺は部屋に行くってだいぶん前に連絡したぞ。」
マタドールは顔をしかめる。
「ああ、ごめんごめん。ずっと朝からビールを飲みながら、フォースについて学んでたんだよ。」
「フォース? はは、スターウォーズか。」
彼はテレビ画面を見て察し、そして部屋に入ると浴室に向かっていった。
「シャワーを借りてもいいだろ? 最近は川で水浴びしかしてないんだ。」

シャワーを浴びてご機嫌のマタドール。
親友のマタドールはアリゾナトレイルのスルーハイカーではない。彼はアトランタから僕をクルマでアリゾナトレイルのトレイルヘッドまで送ってくれたあと、スタートから一緒に数日ハイキングをして僕の誕生日をトレイルで祝ってくれ、そこから僕らは一度別れていた。 マタドールはアリゾナの友人の結婚式に参加して、その後近くのキャンプ場で趣味のトレイルランニングを楽しんでいたらしい。 そして、僕が街に滞在するタイミングで彼はやって来たのだった。
「なあ、なんでこんな辺鄙な場所のホステルに泊まってるんだ? もっと街の近くの方が楽しいだろう。」
浴室から反響した彼の声が響く。
「ここがとにかく安かったんだよ。なんだかとても疲れてしまって、数日休みたかったんだ。だから安い宿をネットで探したら、ここだったんだ。しかし、こんなに辺鄙な場所だとは思わなかったけどね。」
ここもうそうだが、インド人家族が経営しているホステルは安い場合が多い。掃除も行き届いていて申し分なく、トレイルヘッドからさほど離れていない。しかしながら砂漠の中にポツンと取り残されたように立つホステルはハイキングの補給には不便だった。

安宿のランドリーはハイカーの味方。
「確かにここから大きなスーパーマーケットは遠すぎるな。補給はもうしたのか?」
「2日前にウーバーで行って買ったよ。あと、引きこもり用の食料と酒もたんまりね。」
「そのようだな。」
マタドールは大量の空き缶とスナックの袋を見て笑う。
「ところでスケッチ。ジェダが今夜飲みにいこうって言っていたぜ。」
ジェダはアリゾナトレイルの女性スルーハイカーだ。
「ここから街の中心は遠いし、彼女と会うのはやめておこうかなと思ってるんだ。」
「なんだからしくないな。お前ってそんなにノリが悪いやつだったか?」
僕はそう言われて自身の状態について少し考えた。基本的に”NO”と言わないのが僕が海外で旅する時のスタイルだ。しかし、今はどこか腰が重い。もしかしたら意外と36歳という年齢をトレイル上で迎えたことが影響しているのだろうか。
「いや、気分が変わった。行くよ。」
今夜、ハイカーたちに会った方が良い気がした。会えばこの停滞した気持ちも前に進み始めるかもしれない。

久しぶりのロング・ディスタンス・トレイルで僕の足はとても疲労していた。
今宵はどうにでもなれ
しばらくはふたりでスターウォーズを鑑賞して時間を潰し、外が薄暗くなり始めた頃にマタドールのクルマに乗ってトゥーサンの中心街に向かう。30分ほど行くと次第に建物が現れ始め、すぐに建造物で一杯になった。街はとても綺麗に整備されていて、まさしく砂漠の中のオアシスといった感じだ。
駐車場にクルマを停め、すっかり夜になった街を歩く。道を行き交う人は皆、小綺麗にめかし込んでいて楽しそうにしている。灯りが美しく煌めく店舗が並んでいる。乾燥してひんやりした空気に反して街は熱気を放っていた。ハイキングでこれまで様々な街を訪れたが、ここは格段に安全で開放的で輝いている。しかしどこか人工的な雰囲気がする街だった。

クルマで市内へ向かう。
僕は待ち合わせ場所をよく分かっていなかったので、マタドールの背中を追って歩き続けた。やって来たのはとても大きなバーで、中に入るとバーカウンターがふたつあり、客が長い列を作って注文の番が回ってくるのを待っている。どうやらハイカーたちは奥のテラス席に集まっているようだが、とりあえずドリンクを注文するためふたりで列に並ぶ。マタドールに僕はこれまでアメリカで返しきれないほどの借りがあるので、せめてもの御礼としてドリンクをご馳走することにした。
彼の注文が終わると僕の番だが、僕は海外のバーで注文するのが凄く苦手だった。日本でさえそれほど詳しくないのに、異国の地でカクテルを頼むのはなかなか難儀で、そんな時はとりあえずマイタイというトロピカルカクテルを頼むことにしている。これはアメリカで初めてバーに行った時に同行したハイカーがご馳走してくれたカクテルで、思い出深かった。アルコール度数もとても高いので、酔いやすい点も好きだった。

バーはとても繁盛していた。一同身なりは汚かったが、それほど浮いていなかったように思えた。
カクテルを手に奥のテラスに行くと、5人のハイカーが既に楽しそうに話をしていた。彼らは僕に気がつくと「スケッチ!」と声を上げて駆け寄ってきた。
ジェダ、ハッピーアワー、ジョン、マーメイド、モー。全員、トレイル上で会ったことがあるハイカーだった。とても好印象のハイカーばかりなので僕は少し安心する。
僕はひとりひとりと再会のハグをして、ぐいぐいとマイタイを飲む。あっという間にグラスは空になったので、すぐにカウンターに戻りおかわりを持って戻った。
皆の2杯目のグラスが空くと、「もっと安くて良い店で飲み直そう」とハッピーアワーが言った。実は20歳の彼はこの街出身で、この街のことは知り尽くしている。彼の他にモーとマーメイドもアリゾナ在住で、アリゾナトレイルには地元のハイカーがたくさんいた。

僕らはとにかく飲みまくった。
ハッピーアワー行きつけの店はいかにも大学生が溜まっていそうなこじんまりとしたバーだったが、ハイカートラッシュの僕らにはちょうど良く、全員がこの場所で腰を据えて飲む気になっていた。ハッピーアワーの指示で小さなグラスに注がれたウイスキーを飲み、バドワイザーをチェイサーとして飲み続ける。昼から飲んでいる僕はたちまち酷く酔いが回ってしまいフラフラになってきた。
そんな僕の状態はお構いなしにおてんば娘のジェダが大きなグラスにストローを3本挿して端から酒を回し始める。
もうやめてくれ、と心の中で叫びながらハッピーアワーを見ると、彼は50代ハイカーのジョンと腕相撲をしていた。「もう今宵はどうにでもなれ」と僕は心の中で叫んだ。

腕相撲するジョンとハッピーアワー。
全員がひどく酔っ払っている。気がつくとマタドールがジェダを肩車して街を歩いていた。ハッピーアワーは黒いドレスを着た見知らぬ女性と一緒に歩いている。トゥーサンに自宅があるマーメイドは、一度帰宅してスパンコールのドレスを着ている。僕はその奇妙なパレードの流れにただ乗って移動していた。そして、ピザ屋で飲み直し、最後はジェラード屋で散々騒いだ後、その日の宴は終わりを告げた。

ジェラードを食べてご満悦のジェダ。
ハイカーの一体感
僕は帰りのウーバーの中でぐったりとしながら、アリゾナトレイルのハイカーについてぼんやりと思考を巡らした。このトレイルでのハイカー同士の繋がりはとても興味深い。一体感がとても強いのだ。
これまで歩いてきたPCT、CDT、ATのビッグトレイルで僕が仲良くなったハイカーは、なるべくしてハイカーになった人たちだった気がする。日本でアメリカのトレイルを経験したハイカーとアメリカで出会ったハイカーの話題になった時、僕は共感できないことが多々あった。どうも僕が共にしてきたハイカーと、彼らが話すハイカー像がうまく重ならない時があるのだ。
その理由を僕は、ハイカーのコミュニティの種類がお互い違うからではなかろうかと思っている。つまるところ僕らスルーハイカーは、自分と同種の匂いがするハイカーとしか深く繋がることができないのだ。ハイカーにとってそれは性格や好みだけではなく、ハイキングのスタイル、体力レベルも含まれているように思える。このことに気がついたのは、本当に最近だ。それくらいハイカーはトレイルの全体を見渡しているような気持ちになるが、実は案外すごく狭い空間の出来事しか把握できていない。

PCTにて。類は友を呼ぶ。それはハイカー界でも同じことに思える。
思い返せば僕と仲良くなったハイカーはほとんど同じような雰囲気を持っていた。どこかガサツでだらしない、しかし日々の歩行距離はしっかりと稼ぐハイカーたち。そして皆、貧乏で金銭感覚が似ていた。まさに類は友を呼ぶである。約5ヶ月にも及ぶ路上生活をするのだから、皆心地良さを求めて感性が共鳴する相手を探しているのだろう。
しかし、アリゾナトレイルは様々なタイプのハイカーたちが協力しあって歩いている。ハイキングのスタイルが違っても、同じグループで歩いていることが多い。きっとこれはアリゾナトレイルがトレイルとして成熟する一歩手前にあることが大きい。ハイカーたちはトレイルに対してネームバリューを求めてるのではなく、純粋な冒険心と自由な旅を求めてる気がする。つまり、そういう点でアリゾナトレイルには広い意味での同種が多いのかもしれない。

マタドールは「アリゾナトレイルはあと数年でJMT(ジョン・ミューア・トレイル)と同じくらいの人気が出るに違いない」とよく言う。僕はこのトレイルをまだ少ししか歩いていないので断言はできないが、距離感やダイナミックさ、今回のトゥーサンのような街のクオリティからして、とても素晴らしいトレイルで、彼が言うことも頷ける。
トレイルの人気に火が着く前に歩いているハイカーたちはどこか型にはまろうとせず、自由な雰囲気を大切にしているように思える。その緩やかな空気感が僕らを繋ぎ、アリゾナトレイルにいるだけで全員が家族の様な一体感を生み出している。
何か僕はアリゾナトレイルについて深い理解に到達するような気がしたが、ホステルに戻りベッドに倒れ込んだ瞬間に僕の意識はプツリと途絶えた。
砂漠という異世界

トレイルに戻る前は駆け込みで高カロリーの食事をすることが多い。
翌朝は二日酔いだった。ベッドの中でしばらく動けずにいたが、意を決してシャワーを浴び、出しっぱなしにしてあったオレンジジュースを一気に飲み干した。流石に4日もこのホステルに留まっていることはできない。チェックアウトの時間までにパッキングをして脱出するのだ。
食料はまだ買い出して袋に入ったままだったので、個包装のスナックはジップロックにまとめてからフードバックに入れ、そして他の食料を適当に放り込んでいく。あとはトレイル上で毎朝している流れと同じでささっとパッキングを終えた。
そのままバックパックを背負い部屋を出ると、その瞬間に容赦ない日差しが僕に降り注いだ。今年のアリゾナは例年よりも異常に暑いらしい。ここ数年異常ではない年があっただろうか。僕は近くのガソリンスタンドで昼食にバーガーを食べてから、ウーバーを呼んでトレイルに戻った。

砂漠を黙々と歩く。
久しぶりのトレイルで二日酔いだったが、足取りは軽かった。3日間の怠惰な休養が良かったのだろう。平坦な砂漠を分断するように褐色のトレイルがどこまでも続き、その所々に小さなサボテンが生えていた。
僕は砂漠を歩くのが大好きだ。アメリカのハイカーはなぜそんなに乾燥した大地が好きなのかと不思議がるが、僕は生まれ育った島国に全く存在しないこの異世界を愛していた。砂漠に立つと全てが新鮮に感じる。乾き切った大地、ガラガラ蛇の威嚇する音、そして夜には目が眩んでしまうほど空を覆い尽くす星空に、僕はDNAレベルで感動していた。もしかしたら、長く続く我が血筋において初めて砂漠に来た人間かもしれない。いや、きっとそうに違いない。だからこんなに血が騒ぐのだ。

時にハイウェイの下をくぐる。この蛇のグラフィティはアリゾナトレイルの名所。
昨夜はあれほど賑やかだったのに、今はポツリと孤独に砂漠にいる。それを寂しさ半分、楽しさ半分で砂を巻き上げながら歩いていく。気がつけば二日酔いは治っていて、闊歩する小気味良いリズムが僕の体に満ちて、思考は停止してただただ砂漠を突き進む。
途中、ハイウェイ脇の駐車場を通ると何やら騒がしいので覗いてみると、なんと昨夜の面々がそっくりそのままベンチに座ってグダグダと話をしていた。どうやら、彼らはこの地点から歩き始めるようだ。
「おい! スケッチ! 後ろから歩いてきたのか? 元気だな!」
僕を見つけたハッピーアワーが言った。
「めっちゃしんどいけど、まあ、なんとか歩いてるよ。」
「私たちはまだダメだわ。」
ジェダがボーッと遠くを見つめながら言った。彼らはまだまだ昨日のダメージが残っているようで、すぐには歩き出しそうになかった。
「まあ、気楽に行こうぜ。じゃあ、またトレイル上でな。」

二日酔いで全く歩き始める様子のないハイカーたち。
僕はそう言って、歩き続けることにした。これまでのトレイルでは別れの意味も込めてそう言うことが多かったが、アリゾナトレイルでは、本当にまたすぐにトレイル上で会う気がしてならない。
ふたりのトリプルクラウン
その後も平坦なトレイルが続いた。何の変化もないように思えるが、進むにつれてサボテンはどんどん高くなっていき、4、5メートルにも及ぶ巨大なサボテンが山を覆っている景色を見て、奇妙な世界に迷い込んでしまったような気持ちになっていく。

アリゾナトレイルを歩き始めて17日目、250マイル(400km)地点。相変わらずサボテンだらけの変わらぬ景色の中を歩いていた。しかし、気温だけは毎日デタラメで、おとといマウント・レモンを登った時は突如大粒の雹が降り始め、一気に雪景色になった。そこから昨日までは雪の中を凍えながら歩いていた。その悪天候がやっと終わったと思えば、今度は気が狂いそうなほどの日差しになり、今は水を求めて砂漠の中を彷徨っている。

アリゾナは砂漠だと思っていたが標高が上がると雪が降る。
すると突然トレイル上にソファが現れた。家のリビングに置かれるような、二人掛けのグレーのソファだ。ところどころ表面の皮は剥がれて、中のクッション材が飛び出しているが座ることはできそうだ。
僕はバックパックを置いて、勢いよく腰を下ろす。中のサスペンションがギギギギと鈍い音を立てて、僕の体重を吸収して包み込む。少しソファのクッションを楽しんでから、なぜこんなところにソファがあるのだろう? と少し不思議に思った。しかし、トレイル上で生活していると奇妙なことばかり起こる。これまでの出来事に比べると砂漠にソファがあるなんて別に大したことではないような気もした。

砂漠に突如現れたソファ。
しばらく座って休んでいると、ひとりのハイカーが歩いてきた。高身長ですらりと長い足。そしてかなり軽量化されたバックパック。僕を見つけると片手を上げて近づいてきた。余裕があり洗練された仕草に彼は既にロング・ディスタンス・トレイルをいくつか経験したことがあるに違いないと感じた。
「やあ!」
「やあ!僕はスケッチ。調子はどうだい?」
「調子は最高さ。俺はアラジン。よろしくな。」
「よかったら君もソファに座ってみてはどうだい?」
「砂漠の真ん中にソファ。悪くないね!」
彼はそういうとバックパックを地面に下ろして、僕と同じようにどかりと腰を下ろす。
「こりゃ最高だ。ところで君はなんでスケッチって呼ばれてるの? 珍しいトレイルネームだね。」
「その名の通りさ。僕はトレイル上でずっと絵を描いてるからね。」

ハイカーに会うと名刺がわりにスケッチブックを見せる。
僕はバックパックからスケッチブックを取り出して、彼に渡した。彼は1枚1枚興味深そうに眺めた。ほぼ毎日描いているスケッチブックは僕にとっての旅の記録で、自分というハイカーを知ってもらうのにいちばん手っ取り早いギアである。
「もしかして、他のトレイルもたくさん歩いてるのかい?」
アラジンはスケッチブックを捲りながら言った。
「僕はトリプルクラウナーさ。多分だけど君もそうだろう?」
「当たり。なんでトリプルクラウナーって思ったんだい?」
「それは君の雰囲気と、あとアリゾナトレイルはトリプルクラウナーが沢山いるからさ。」
トリプルクラウナーとはアメリカの3大トレイルであるPCT、CDT、AT全てを踏破したことがあるハイカーのことを指す。
実際のところ、トリプルクラウナーはトレイル上ではかなり珍しい。なんたって多くのハイカーが一世一代の大冒険としているロングディスタンストレイルのスルーハイクを3回もするなんて、よっぽどの暇な変わり者だからだ。しかし、このアリゾナトレイルにはそんな希少なハイカーが沢山いた。それは3大トレイルを歩いたハイカーにとって、アリゾナトレイルはちょうど歩きやすい距離で、そして起伏の少ない乾燥地帯を突っ切ることができるからだと思う。さらにアリゾナトレイルは砂漠だが定期的に街に下りることができる。
この点がとても大切で、CDTで孤独に砂漠の中を彷徨い続けた経験があるトリプルクラウナーたちからすれば、とても難易度が低く感じる。そして基本的に雨が降らず、ライム病をもたらすマダニの心配もない。このような条件が整うと、とことんギアを軽量化することができる。だから、僕らにとってアリゾナトレイルは超軽量のバックパックを背負って平らな土地を疾走することができる夢のような遊び場なのだ。
かくいう僕も今まで軽量化には苦心し続けていた。やはりある程度の経験や度胸がないと、今まで持ち続けていたものを手放すことは怖いのだ。しかし、このトレイルに関しては上記の理由から思い切って軽量化にチャレンジしてみようと考え、これまで使っていた60Lから36Lのバックパックに変えている。
アラジンはスケッチブックを僕に返すと、スッと立ち上がってバックパックを背負った。

すごい速さで歩くアラジン。
「さてと。そろそろ行きますか。」
「そうだね。そろそろ行きますか。」
僕は急いでバックパックを背負って、もう歩き始めている彼を追った。ここからはトリプルクラウナーのふたり旅が始まるのかもしれないな。そう思って心躍らせたが、それも最初の30分ほどだった。アラジンの歩くスピードが速すぎるのだ。彼は颯爽と歩いているが、僕はついて行くのがやっとだ。いよいよこれはもう無理だなと諦めて、小便をするから先に行ってくれと言って、その狂気的なスピードのハイキングから離脱した。彼は見る見るうちに離れていき。すぐに砂漠の中の小さな粒になってしまった。
何がトリプルクラウナーだ。僕と彼は全然ハイカーとしての質が違うではないか。彼への憧れと共にどれだけ距離を歩いても強靭なハイカーになれぬ自分を嘆いた。

荒野をひたすらに歩く。
ドクターピザの店
延々と続く砂漠を何日も歩き続けた。体も完全に慣れ、どれだけ歩いても疲れを翌日に持ち越すことはなくなった。毎日が自由で気持ちの良い日々だった。
アリゾナトレイルの最大の困難といえば水の確保だ。砂漠にはもちろん川などなく、トレイルエンジェルなどがタンクの中に水を入れて置いてくれているウォーターキャッシュや、家畜用の貯水タンクから手に入れなくてはならない。しかし、もともと話で聞いていたよりも、水の確保は容易だった。とにかく水を見つけたら5リットルくらい運んでしまえば、翌日にはきっと良い水場を発見できる。

こんなに巨大なサボテンを僕は見たことがない。
トレイルの周辺には相変わらずびっくりするほど大きなサボテンが所狭しと生えていた。あと少しでカーニーの街に続くヒラリバートレイルヘッドに到着するところで、ふたりのハイカーに出会った。ひとりはかなり古いフレームバックパックを背負ったスティンキー、そして開口一番にインスタグラムのアカウントを紹介してきたジェシカだ。このふたりのことはハイカーの名前を記入するレジスターで常に僕の少し前に名前が書かれていたので存在はずっと気になっていたが、ここでやっと追いつくことができた。僕らは話をしながら歩き、道路に出るとすぐにヒッチハイクを開始する。すると物の数分で1台のクルマが停まり、僕らをカーニーの食料品店まで乗せてくれることになった。

スティンキーとジェシカと歩く。
カーニーの食料品店に入ると中には数人のハイカーがたまっていた。その中にはアラジンもいて、話を聞くと彼は1日前に到着していた。彼を除いて他のハイカーたちは初めて見る顔だが、皆とても個性ある格好をしていて、ベテランの風格がある。
「ドクターピザに会ったかい?」
アラジンが僕に言った。ドクターピザは地図アプリのコメント欄にカーニーに行ったら絶対行くべきと多くのハイカーが書いてるピザ屋のオーナーらしい。

旅慣れした雰囲気を醸し出すハイカーのジェンガ。
腹ペコな僕とスティンキーとジェシカはすぐにトレイルに戻ろうとしている彼らと別れて、急いでピザ屋を目指したカーニーはとても小さな街で、15分もあれば街の端から端まで歩くことができた。ピザ屋は街の中心にあり、”PIZZA”と書かれた小さなネオンの看板が点滅している。店の中は僕が思っていたよりもずっと広く30席ほどあり、奥にはレトロなゲーム機が並んでいた。客はふたりしか見当たらなかったが、キッチンではスタッフがデリバリー用のピザを忙しそうに焼いていた。
僕らはそれぞれピザを注文し、運ばれてくるまでビールを飲みながらダラダラと過ごす。外は40度近い灼熱だが、店内はエアコンを使わずとも涼しかった。

ハイカーハンガー。僕らはいつも腹ペコ。
3杯目のビールを注文しようとしていた時、店の扉が開き立派な白髭の小太りの中年が入ってきた。
「ようこそハイカーたち! 私はドクターピザだ!」
彼はそう叫ぶと豪快に笑った。そして僕らの方に歩み寄ってきた。
「不在ですまなかったね。ハイカーをピックアップしてたんだよ。」
彼の後について3人のハイカーが店に入ってきた。驚くことにハッピーアワーとモーとジョンだった。彼らも僕を見つけて驚いていたが、僕も彼らとは今回の旅でとても強い縁を感じていた。そして、なぜか出発したはずのアラジンも戻ってきた。さらに数人のハイカーが集まってきて、汚いバックパックで溢れた店は僕らの宴会場に早替わりした。

陽気なドクターピザ。
みんな、たらふくピザを食べてビールを飲む。ドクターピザはとても陽気な人で、ビリヤード台に腰をかけて歌い始めたかと思うと、次の瞬間には店の柱でポールダンスをしている。彼は心の底からハイカーを歓迎しているようで、その幸せな波長が皆に伝播して笑顔になった。
酒好きのハッピーアワーはずっとビールをピッチャーで頼んで飲んでいる。僕は彼の横にいたものだから、勝手に注がれるビールを飲んでいるうちにいつぞやの夜と同様に気がつけばかなり酔っていた。
ピザ屋の後はお決まりのバー巡りをした後に、スティンキーとジェシカが泊まっている宿のレストランに落ち着いた。みんなかなり酔っ払っていて、突如として開催された賭けビリヤードは誰ひとりとして正確にキューで球をつくことができない。飲み疲れてしまった僕は椅子に深く座り、スティンキーとアラジンの戦いを眺めた。
スティンキーも相当酔っ払っていて、毎回変な体制で球を突こうとする。彼は衣服を洗濯中でアンダーウェアを履いていなかったので、おかしな体勢になるたびにブカブカのショーツの裾から、彼の睾丸がゆらゆらと揺れているのが見えた。僕はそれを見ていると次第に気分が悪くなってきて夜風に当たることにした。

玉を打つたびに彼の玉が見える。
外に出ると、街は真っ暗で店の中から漏れる音が寂しく響いている。僕の今日の寝床はどこになるのだろうかと考えた。もちろんカーニーに到着してから宿の手配などしていないし、ハッピーアワーたちも同じだ。おそらく今夜は皆でスティンキーの部屋に流れ込むことになるだろう。
無数の星が気持ち悪いくらいに煌めいている。そのいくつかは落ちてきそうだと考えていたら、本当にひとつ星がスッと流れて消えた。
それが現実なのか幻覚なのかもよくわからなかったが、突如僕がこれまで積んできたハイキングの経験や実績など、とてもくだらないものに思えた。ロング・ディスタンス・トレイルは今日のようなハイカー的な1日の連続であり、1日は瞬間の連続だ。とりあえず今を、このくだらない夜を楽しまないでどうする。
そう思って、僕はもう1杯酒を飲むために皆のいる店内へ戻っていった。
【#3へ続く】