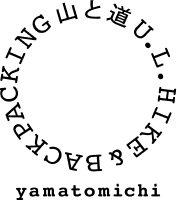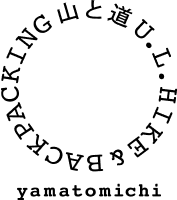#7 イェンス・イェンセン(拠点プロデューサー)
写真:三田正明
#7 イェンス・イェンセン(拠点プロデューサー)
写真:三田正明
山と道というこの奇妙な山道具メーカーの特徴のひとつは、アウトドアの文脈だけには収まりきらない、実に様々なバックグラウンドを持つ人々との関わりがあることかもしれない。
この『人・山・道 -ULを感じる生き方-』では、そんな山と道の様々な活動を通じて繋がっている大切な友人たちを訪ね、彼らのライフや思考をきいていく。一見、多種多様な彼らに共通点があるとするならば、自ら背負うものを決め、自分の道を歩くその生き方に、ULハイキングのエッセンスやフィーリングを感じること。
山と道に「拠点プロデューサー」として関わるイェンス・イェンセンさんは、自らの家や職場、キャンピングカーまでなんでもDIYしてしまう。山と道でも、当初はブランディングや海外向けのコミュニケーションを担当していた彼が、現在ではいつのまにか店舗や工場などのプロデュースも行っているなど、自ら仕事までDIYしてしまう。
そんなふうに、いつだって「やりたいようにやる」彼のマインドと、山と道が重なる場所とは。
リノベーション精神の原点

現在改装工事中の『梶原山荘』にて。
鎌倉の源氏山にも近い高台にひっそりと佇む『梶原山荘』。この秋にオープンするこの場所は、山と道の新しい施設だ。築約60年の民家をリノベーションした空間の内装をデザインしたのは、デンマークからやって来て、20年以上になるイェンス・イェンセンさん。
DIYとリノベーションを通じて独自の空間美学を育んできたイェンスさんは、神奈川県鎌倉市の『山と道大仏研究所』や兵庫県豊岡市の『豊岡ファクトリー』の内装デザインを手がけるなど、山と道と深いつながりを持っている。
デンマークで生まれ育ったイェンスさんが日本にやって来て、鎌倉を拠点に暮らすようになったきっかけは、10歳の頃に見たアメリカ・NBC制作の時代劇ドラマ『将軍 SHŌGUN』だった。
「『将軍』で初めて日本という国を知って、『なんかおもしろそうな国だな!』と思ったんだよね。日本について調べるうちにすごく興味が湧いて、行ってみたくなった。それで日本語を勉強し始めたんだよ」と、少年時代に衝撃を受けた日本文化との出会いを振り返る。
デンマークの高校を卒業後、ロンドン大学で日本語と言語学を専攻。2002年の卒業後に日本へ移住した。その後3年間、日本の設計事務所でプロジェクトマネージャーとして働き、設計デザインの基礎やCADの技術を身につけた。
さらにデンマーク大使館でも勤務し、商務官としてデンマーク企業の日本進出を支援したほか、広報担当官としてデンマーク文化を日本に広める活動にも携わった。
「学生の時に考えていたプランでは、日本の建築がすごい好きだったから、日本に行って建築設計士になりたいなと思ってた。でも東京に来た時に、すっごいがっかりしたんだよね。デンマークとかイギリスで見ていた日本の建築に関する本は、たとえば安藤忠雄とか、もうめっちゃかっこいいモダン建築ばっかりだったんだけど、実際に東京の建物を見てみると、『あんなかっこいいモダン建築はどこにあるの?』みたいなね(笑)。これはちょっと違うなと思って、設計士になるのをやめたんだよ」
日本で設計士になる夢は手放したものの、建築や設計への興味が失われたわけではなかった。その後も、DIYのリノベーションを軸に、自邸やさまざまなプロジェクトで空間づくりを手がけるとともに、山と道のプロジェクトにも深く関わっている。
その原点はデンマークでの環境にある。父親が木工の教師だったため、工務店のような木工の機械や道具がある自宅の工房は子どもの頃の遊び場だった。DIYの精神は幼少期から自然と身についていたという。
「小さい頃から、自分の部屋の床を張ったり家具を作ったりしてたんだよね。家に木工の道具がたくさんあったから、ものづくりや家づくりは当たり前のことだった」
デンマークの義務教育(日本の小・中学校にあたる)には必須科目として木工の授業があるそうで、イェンスさんも中学1、2年生の頃、週に一度2時間の木工の授業を受けていたという。
家庭環境とデンマークの教育。こうした背景が、イェンスさんのものづくりへの深い理解と情熱の原点となっている。
この原体験は、その後のリノベーション実例にも活きている。これまでにも鎌倉エリアを中心にして日本各地で、手を加えることで面白くなりそうな物件を見つけてはリノベーションして貸家にしたり、外部からの依頼を請け負ったりして、リノベーションによる空間づくりを重ねてきた。

リノベーションとMYOGの関係
そんなイェンスさんと山と道の出会いは、今からおよそ10年前にさかのぼる。イェンスさんがジャパン・エディターとして関わっているイギリスの『Wallpaper*』誌で、鎌倉の記事を執筆したのがきっかけだった。当時の山と道は、立ち上げからまだ2〜3年ほどの頃だった。
「その頃、キャンプはよくしてたけど、ハイキングや登山は全然やってなくて、ULハイキングなんて言葉も聞いたことがなかった。取材をするために鎌倉で誰か面白いことをしてる人はいないかな? って友人に相談したら、山と道と夏目さんを紹介されて。プロダクトの見た目はかっこいいし、軽いし、すごいなと思ったけど、山道具のことはわからなかったから、その時は、あんまり評価できなかったよね」
だが、代表の夏目夫妻へのインタビューを通じて「なんか面白いな。かっこいい日本のものづくりの人たちだな」と感じたという。
その後も夏目と連絡を取り合う中で、山と道の英語版ホームページの作成やブランディングの相談を受けるようになり、関係は深まっていった。転機となったのは、山と道のメンバーと共に尾瀬を訪れた時だった。
「スタッフの何人かが尾瀬のハイキングに誘ってくれたんだよ。その時に山と道の道具を身につけて歩いて、タープで寝たりしてね。全てが初めての体験だったけど、『ULってこういうことなのか!』って理解できた」
この体験を通じてULハイキングの思想に強く共感するようになり、その認識は大きく変わった。「ULハイキングの、必要な道具がなければMYOG*するという考え方が、リノベーションとすごく似てるなと感じたんだよね」と、ULの精神とリノベーションの親和性を見出したそうだ。
*MYOG = Make your own gearの略で、ULハイキングの黎明期、ULに適した軽量な道具がほぼマーケットに存在しなかったため、必要な道具を手作りしたり、既製品を改造して使っていたことに端を発するULハイキング文化のひとつ。それが高じて後に多くのガレージブランドが生まれることになった。
山と道らしさを体現できる場づくり
「現在、僕と山と道との関わりは大きくふたつあって、ひとつは英語の部分の仕事だね。海外とのコミュニケーションや編集、監修、海外案件のコーディネーションを担当している。そしてもうひとつに拠点作りがある。オフィスやお店とか、言うなれば基地のような場所をプロデュースしたりデザインしたり、その一部を作ったりする仕事が多いね」
イェンスさんは、こうして山と道らしさを体現する場をこの数年で次々と生み出している。現在手がける『梶原山荘』も、奥さんと一緒に見つけた物件だった。


古い一軒家をリノベーションして作られている『梶原山荘』。基礎や柱は残されるものの、ほぼすべての部分に手を入れる。
「夏目さんと『山と道に来るお客さんが泊まれる施設があるといいね』『会社とは別にオフサイトでミーティングできる場所が欲しいね』と話していた時に、妻のまりこが見つけてきた物件だった。これは山と道にぴったりかもしれないなと思って夏目さんに見せたら、盛り上がって山と道で買うことになった」
源氏山公園や葛原岡神社に近く、瑞々しい緑が鬱蒼と茂る小径に佇む、物語を感じさせる古い一軒家。車が通れない急な坂道の途中にあり、一見「住みにくそう」「使いづらそう」と思えるその物件に価値を見出したのは、イェンスさんならではの感性だろう。
車を軸に行動を考えた場合には利用しづらい物件なのだが、それを「歩く」視点に切り替えれば、 山越えのルートでおよそ2.5km、3~40分の距離にある大仏研究所までハイキングを楽しみながら行き来できるのだ。鎌倉らしい自然の中を歩きながら、『山と道大仏研究所』と『梶原山荘』を行き来する新たなルートが立体的になるという面白さがある。
「山をまたいで行き来できるなんて、山と道らしくていいなと思ったんだ。ぴったりだなと」
デンマークで過ごした少年時代から培ったイェンスさんならではのセンスと技術が、山と道の仕事で発揮されていることがよくわかる。
「山と道の思想に無理に合わせているわけじゃない。でも、もっと面白くなると思ったら提案する。結果、信頼されていると感じるし、やりたいようにやらせてもらえている。リノベーション自体が山と道っぽいやり方だと思うし、本当にMYOGとすごく似てるんだよね」
土地と物件が本来持っている魅力を活かす
『豊岡ファクトリー』は2024年に兵庫県豊岡市に作られた。古い鉄工所を借り、イェンスさんのディレクションでリノベーションし、1階にミシンの作業場、2階に事務所と休憩スペースを設けた。『豊岡ファクトリー』では製品づくりだけでなく、ものづくりの実験も繰り返されている。




廃屋のような状態だった築70年以上の古い鉄工所をリノベーションして作られた『豊岡ファクトリー』。(写真:澁谷亮一)
「リノベーションで大事にしているのは、場所の魅力を最大限活かすこと。山の中なら山小屋らしさを出すし、街の中なら街のエネルギーとどうつながるかを考える」
イェンスさんがリノベーションした物件を見ていると、その建物が本来持っている魅力や面白さを最大限に引き出すために、大切な部分は残しつつ、無駄なものは排除して進められているのがよくわかり、なるほどと理解できるのだ。
物件探しとリノベーションコンセプトを担当し2023年にオープンした『山と道京都』も、元は風俗街だったが、いまでは個性的なショップが並び、カルチャーの香る街へと変わりつつある「五条」というエリアを選んだ。その土地や建物の歴史や文化を活かし、イェンスさんのエッセンスが加わることで新たな輝きを放つ空間に姿を変えるのだ。


京都市下京区の五条エリアにある『山と道京都』。(写真:大竹ヒカル)
今を楽しむのが一番、という思考
ULの考え方は、イェンスさんの設計やリノベーションに大きな影響を与えている。
「ULの『あるものをどう活かすか』、その感覚がすごく好き。山と道に出会ってから自分の中でも色々変化があったけど、暮らしに関してもずいぶんものを減らしてシンプルになったし、仕事でも、空間づくりに影響が出たよ。たとえば『梶原山荘』はほとんど仕上げをしてないんだよね。普通は石膏ボードの上に壁紙を貼るけど、うちは普通外壁の下地材に使うボードを裏返して使うだけで、そのまま見せる仕上げにしている」
少ないもので最大の価値を引き出す姿勢は暮らし全般に及び、旅のスタイルも軽量になったという。最近訪れたスリランカの旅では4kgの荷物で10日間過ごしたという。
「荷物が軽くなることで心も体もどれだけ自由になるかって思う。それって、旅の荷物も家にある荷物も、人生の荷物も同じなんだよね。最近は、過去のことはもういいやと思ってるよ。そりゃあ将来のことも少しは考えるけど、それもずっと考えてもしょうがないから。とりあえず今、すぐにでも行動できるようなことばかりを考えて、なにかあった時にそれに対応できるようにしているね。それってハイキングとすごく似てると思う。いきなり雨が降ったらどうしよう、みたいに準備はするけど、なによりも今を楽しむのが一番だと思う」

日本の職人へのリスペクト
学生時代には日本のモダン建築に憧れていた一方で、日本の伝統的な家づくりにも興味を持っていたというイェンスさん。日本の家づくりに脈々と流れる伝統的な技術には敬意を払いつつも、日本ならではの家づくりを取り巻く環境には疑問があったようだ。
「日本って建物、特に家に関しては古いものをあまり大事にしないんだよね。その家が持っている歴史とかも無視してすべて更地にしてしまうことが多い。そうすると、歴史も想いも全部消えるわけ。その理由はたぶんみっつあって、まずは相続税の問題。大きい家や庭があっても次の代に引き継いだ時にめちゃくちゃお金がかかるから、仕方なく壊して分けてないといけないことは多いよね。もうひとつは素材。日本の家はもともと木とか和紙を用いて造られた家だよね。短時間で建てやすい素材とも言えるし、欧米の石やレンガ造りの家に比べると耐久年数は短くなる。そして、江戸時代からは火事や地震があったらすぐに壊して新しい家を造るというスクラップアンドビルドの思想が主流になったから、その概念が現在も残っていると思うんだよ」
イェンスさんのリノベーション哲学の大切な部分として、家が持っている歴史も大事にすることがある。自身がリノベーションを手がけるプロジェクトでは、古いものをなるべく壊さずに、その家が持つ本来の魅力を活かすことを心がけている。
欧米に比べて家の長期的な保存を志向しない日本の事情には疑問を持っているものの、日本の家づくりの職人文化は世界に誇るものだと語るイェンスさん。山と道の現場を通してものづくりの職人文化への尊敬も深まったそうだ。
「日本の職人さんのこだわりは本当にすごいんだよね。すごく面白いし学べることがいっぱいある」
そんな日本のていねいなものづくりと、イェンスさんのDIY精神は融合し、山と道のプロジェクトにも豊かな彩りを与えている。
ULを体現するように、軽やかで柔軟に生き、常に新しいことに挑戦し続けるイェンスさん。
「僕はすごく飽きっぽくて、同じことずっとやれないタイプ。だから、どんどん新しいものが入ってきた方が楽しい」と、自身の行動の原動力を語る。
「今を楽しむのが一番」何度も口から出てきたその言葉通り、イェンスさんのつくる空間も暮らしぶりも軽やかで、何より楽しい空気に溢れている。

デンマーク生まれ、2002年より日本在住。鎌倉は2013年より4年ほど手がけてDIYでリノベーションした家に住む。山と道の不動産開発や海外向けの英語コミュニケーションをお手伝いしている。他には、イギリスの『Wallpaper*』誌のジャパン・エディターや国内外のメディアに執筆も行う。ハイキング歴はそう古くないが、山と道に出会ってから鎌倉の近隣の山やちょっと遠出して山登りを楽しみ始めている。