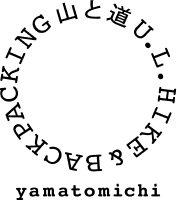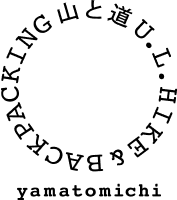山と道HLCディレクターの豊嶋秀樹をホストに、身体行為としてのハイキングをリベラルアーツ(生きるための学問)として捉え、同じく身体行為である「見る」ことや「聞く」こと、「食べる」ことなどを手掛かりに、ハイキングのその先にある価値と可能性を探っていく連載『HIKING AS LIBERAL ARTS』。
#5前編となる今回は、外国人初のチベット医(アムチ)となり、現在は長野県上田市で薬に関する講演やワークショップ、医薬品や薬草茶の販売を行っている「森のくすり塾」を主宰する小川康さんを訪ね、私たちの身近にありながら遠い存在である「薬」について話を伺った。
そもそも自然や人々の暮らしの中にあったはずの「薬」が、どのように私たちと切り離されていったのか。そしてそれを、再び私たち自身の手に取り戻すためのヒントとは。
取材メモ:豊嶋秀樹
『HIKING AS LIBERAL ARTS』は、ゲストのライフストーリーを聞くというよりは、その方の専門そのものについて教えてもらい、どうやって自分たちの生活に役立てられるかを読者の皆さんに考えてもらうこと、そして、それら「生きる術=リベラルアーツ」が、僕たちがハイキングで体験したり、感じたりしていることともつながっていると感じてもらえたらいいな、という思いで続けています。
これまでに、キュレーターのロジャー・マクドナルドさんには「見る」、働き方研究家の西村佳哲さんに「聴く」、料理家の三原寛子さんは「食べる」、ヨーガ実践者のDONIさんには「呼吸する」というテーマで話してもらいました。これらはすべて、身体と向き合うための基礎的な「技術」だと捉えています。
今回は、その「生きる術」として、小川さんに「薬」についての話を伺いたいと思います。

小川康 富山県出身。1970年生まれ。「森のくすり塾」主宰薬剤師。チベット医/薬教育研究者。ボランティア団体、薬草会社、薬店、農場などに勤務後、1999年1月よりインド・ダラムサラにてチベット語・医学の勉強に取り組む。2001年5月、メンツィカン(チベット医学暦法大学)にチベット圏以外の外国人としては初めて合格し、2007年卒業。晴れてチベット医(アムチ)となる。チベット社会で医師として認められた後、日本に帰国し「薬房・森のくすり塾」を開設。2015年3月、早稲田大学文学学術院を卒業。修士論文のテーマは「薬教育に関する総合的研究」。著書に『僕は日本でたったひとりのチベット医になった ヒマラヤの薬草が教えてくれたこと』(径書房)『チベット、薬草の旅』(森のくすり出版)がある。
身近な自然にあるもので薬を作る
――小川さんとは13年前に初めてお会いしたんですよね。そのときに聞いた葛根湯の話がすごく印象に残っていて、あらためて今日聞きたいなと。
葛根湯は実は家でも作れるんですよ、という話をしたんですよね。手に入りづらい素材はひとつあるけれど、それ以外は身近なもので揃うよと。
――そう、それを聞いてすごく驚きました。僕の中では、薬ってどこで作られているか分からない、遠い存在だったから。でも、自分で知っていれば集めて応用できる、という話がすごく心に刺さったんです。薬は誰かが作ってくれるものではなくて、自分で関わることができる「知恵」なんだと。
実は、あの話には続きがあるんです。葛根湯の原料となるクズの根を掘るところからやってみようと思って、長野の山で葛根湯を作るというイベントを企画しました。僕がクズの根っこを見つけたのは、2015年頃の豪雨で山が崩れたときに、山肌を見ていたら発見したんです。それに気づけた人は、たぶん僕しかいなかったと思います。これが50年前だったら、おそらくもっと多くの人が気づいたと思いますね。昔は、薬草の採取を仕事にしている人が、今より多くいましたからね。
とにかく、クズの根を発見したわけです。で、その次のステップがありまして、あのクズの根っこは誰の山なんだろうと調べるわけですね。その結果、自由に掘っていいという確認を取りました。
そして、第3段階。今度はクズの根掘りと葛根湯づくりをイベントにしたいと考えたわけです。「じゃあ一緒にやりましょう」と言ってくれた村役場を動かして、東京から人を集めました。20名以上が参加してくれたと思います。
それで皆さんと一緒に掘りました。山に自生していた本物のクズの根っこを使って、葛根湯を作ったので、イベント的には成功したのですが、掘り出すだけで疲れ果ててしまいましたね。クズの根っこって、すごく太くて、掘り出すのは想像を絶する大変さなんです。あまりにも労働が激しすぎて、途中から何をやってるか分からなくなってしまいました(笑)。でも、このクズの根を掘るという行為は、薬が自分たちの暮らしから遠い存在ではない、ということを教えてくれましたね。

小川さんのクズの根掘りと葛根湯づくりワークショップの模様。(写真提供:小川康)
――クズの根以外のほかの材料はどうやって調達したんですか?
それらもできるだけ自分たちで調達しました。葛根湯にはクズ、シナモン、ショウガ、ナツメ、シャクヤク、カンゾウ、そしてマオウが入っています。シナモン、カンゾウとマオウだけは同じようには手に入らないので、事前に用意しておきました。
――マオウが入らないと葛根湯として成立しないんですか?
ひとつの薬草には約5,000〜10,000種類もの成分が入っています。ここでは分かりやすく5,000としましょう。例えば5,000人の村があって、そのうちのひとりにスーパースターがいたとしたら、その村のイメージがひとりのスーパースターのイメージになりかねませんよね。それと同じで、マオウという薬草には、エフェドリンという、5,000分の1級のスーパースターがいるんです。マオウは、ほぼこのエフェドリンの薬効で支配されているというわけです。

マオウの花。発汗、解熱、鎮咳といった作用があるエフェドリンを多く含み、根茎が生薬として利用される。(写真:Adobe Stock)
ところが、ひとりの有名人もいない村もある。それが「ハーブ」と呼ばれるものです。なんとなくまったりしていて、これといった特徴もない。香りを楽しむ優しい人たちが集まっている村のような存在です。
――なるほど。ハーブは「これに効く」と断言するのが難しいということですね。
そうなんです。「これがこれに効く」ということは、5,000も成分があると分からないですよね。つまり、何が言いたいかというと、薬草というのは、本来それほど言語化に向いていないということなんです。無理やりでもいいから一生懸命言語化しないと、みんな納得できないならば、「納得しなくていいんじゃないの?」というのが僕が言っていることなんです。
腑に落とすのは現代医学だけでいいじゃないでしょうか。現代医学に用いられる薬はひとつの成分だけでできているから、腑に落ちるわけなんですね。いわゆる原因と結果が1対1の単純系。原因と結果が複雑に絡み合う複雑系との違いがそこにはあります。
僕、大学の薬学部で原子レベルまで勉強しているんですよ。もっと言うと、電子レベルまで勉強しました。だからこそ、5,000もの成分を持ち、カオスそのものである複雑系の薬草と単純系である現代医学の薬を同列に語ることの不自然さが、すごく分かるんです。ですから、僕は薬草については、あまり「これがこれに効く」などと言葉にしづらいんだということを、これからのトレンドにしようと考えています。
――「腑に落ちない」っていうのは、どういう状態なんですか?
よく分からない、ということですね。このハーブが何に効くの?と聞かれたときに「飲んでみればいいんじゃない? 何かに効くかもしれないよ。昔から体を温めるとか言われてますしね」という感覚じゃだめかな、ぐらいな感じです。腑に落とすために、みんな一生懸命にひとつの言葉に落とそうとするんですけど、薬草に関しては、それはとても不自然な話なのです。

長野県上田市にある『森のくすり塾』は、高台に立つ神社の森のほとりにある。
口承口伝で伝わる薬草の知恵
――薬草をもう少し日常的に僕たちの生活に取り入れることができるといいですね。何か注意が必要ですか?
現代薬は1個の分子なんですよね。たとえばアスピリンのレベルになると、お医者さんが処方するものなので、それを自分たちで判断しろというのは無理な話なんですが、現代薬ではない薬草は、本来、僕たち自身で判断できるものなんですよね。でも、自分で服用してみて、「あ、これいいかも」っていうことを常日頃から練習しておかないと分からないんです。だとするならば、自分が飲むものを選ぶためには、色々なものを試してみる。そして、自分の体の変化を観察することが重要になります。
ですが、民間療法の本などを読んで、「ビワの葉が癌に効く」って書いてあったりしたら頭に残ってしまい、脳の回路が固まってしまうんです。そうなると、体に合っていなくてもずっと飲み続けてしまったりする。身体の声が聴けていない状態ですね。そうならないためにも、普段からトレーニングをして、自分の体の声に耳を澄ませることが大切なんです。
――どのようなトレーニングをするのでしょうか。
普段から、自分の体の声を意識することですね。そして、あまり本を読みすぎないこと。文字から入らないということですね。薬草は口承口伝に向いていますから。文字から入る知識と、耳から入る知識とでは、最初の入り口が違うんです。例えば野球をする時に、野球入門を読むことから入る人って、ほとんどいないと思うんですよ。みんなまずはキャッチボールからやってみますよね。そして、ちょっと分からなくなったら本を見る。
僕からすると、都会で薬草を勉強してる人って、そういうことをしている感じです。だけど、田舎のおっちゃん、おばちゃんたちの薬草の知識は、耳から入った伝承なんです。「ドクダミはなんとなく効くんだよ」ぐらいでいいんですよ。薬草の知識は、耳から耳へ、口から口へ伝わるものなんだということを、僕はワークショップで伝えています。そういう意味では、文字から入るべきではないというのが、最近伝えている薬草との向き合い方です。
――普段から自分の身体の声に耳を澄ませる、というのは、具体的にはひとつひとつ自分で試していく、ということでしょうか。
『日本人には2種類いる:1960年の断層』(*1)という本で知ったのですが、昔は出産は主にお産婆さんが行い、育児は身近な年長者がアドバイスしてくれていたのですが、1960年ころから専門書が流通したことでお産婆さんなど年長者よりも、専門家の意見を優先するようになったそうなんですよ。加えて、「今まで隣のおっちゃん、おばちゃんたちが話していたことは、どうやらみんな迷信っぽいから、それよりも専門家の話を聞こう」という空気が強くなっていった。それで一気に知識の構造がいわゆる伝承型ではなく、学者崇拝型の、文字を介するものになってしまったらしいのです。それを読んでいたときに、「あ、薬草もまさにそうだな」と思いました。
(*1)『日本人には2種類いる:1960年の断層』(岩村暢子著・新潮社) 1960年を境に、日本人の生育環境が大きく変化し、これ以降に生まれた「60年型」世代は「新型の日本人」となったと論じる日本人論。
――おっちゃんやおばちゃんに聞こうよ、というのはいいですね。
僕なんか、毎日お風呂でトレーニングしている感じです。近所にある温泉に毎日行くんですけど、自分で言うのもなんですが、そこでは55歳で若手のホープ。人気者ですよ。アイドル状態なんで、おじいちゃんたちにいつも可愛がられています。そのおじいちゃんたちの何気ない会話から、薬草を学んでいるとは、まさか誰も思っていないと思います(笑)。本当に、毎日行っていても新しい学びがあるんです。
お風呂の中だからメモれないんだけど、耳で聞くっていうトレーニングと言えます。風呂の中って音が反響するし、本当に聞き取りにくいんですけど、彼らが発する言葉のわずかな語尾から、話を想像して頷いていくんですよ。英語より難しいですよ(笑)。そういうことをしながら思うのは、薬草を語る時は、耳から耳へと伝承して、あえて文字にしないということも大事なんだろうな、ということです。

如来が描かれたチベットの掛け軸。
日本における医学の歴史と登山の歴史
――日本の医学の歴史は、どんな歩みを辿ってきたんでしょうか?
中華思想とインド思想。いわゆる思想の発信源である彼らにとっての日本は「辺境」なんですよね。僕が学んだチベットと日本は、梅棹忠夫さん(*2)の説によると人類学的に似ているというんですよ。日本は中国という中華文化の辺境で、チベットはインドという文化の辺境。どちらも常に中央を向いて、「何かありがたいものが来ないかな」と願っているという意味では似ていると、僕もちょっと思うところがありますね。
でも、大きく違う点があります。日本人は、よその国に行くと珍しいものを食べたがります。一方、チベット人は、ずっと同じものを食べたがります。やはり、基本的に日本人はいろいろなものを試してみたいし、よその国に行ったらそこの文化に染まるし、相手に合わせる。日本人はそういうところがありますよね。たとえばヒンドゥー教徒のインド人が日本に来ても、神社に観光はするかもしれないけれど、信仰したり、真似事は絶対しないですよ。
僕たち日本人は2000年の歴史の中で、いろいろなものを試してきました。医学に関していえば、最初の先生が朝鮮でした。3世紀か4世紀の頃。で、次が中国ですね。中国の医学を取り入れました。16世紀になると南蛮渡来の時代になって、今度はポルトガルを先生にします。そして、江戸時代になってオランダ医学になるんですよ。そのままオランダ医学でいけばいいのに、明治時代になってドイツ医学になった。そして、第一次世界大戦が終わって、アメリカ医学になったというわけです。分かりやすく言うと、常にコロコロと師匠を変えてきたという医学の歴史があります。ですから現在における日本の医学を表現するときに、ドイツに象徴される「西洋医学」という言葉は適切ではありません。「アメリカ医学」というのが非常に的確な言葉です。ドイツでは抗生物質の乱用を避け、自然治癒力や代替療法を重視する傾向にある一方、アメリカは抗生物質を多用し、日本はそれに追随しています。
明治維新の時、日本はイギリス型の横断的にさまざまな知識を学ぶリベラルアーツにするか、ドイツ型の分科型にするかで議論して、結局ドイツ型を選んだ。だから薬学なら薬学、有機合成なら有機合成だけを突き詰める。それがどういうことかと言うと、効率的に発展はしたけれど、社会とのつながりを考えない方向になったんです。
当時の日本は、ドイツ型の方が発展が早いことを見抜いたんですね。完全にマニュファクチュア、分業にしてしまう学問を突き詰めさせる。リベラルアーツ型ではない道を選んだのが、今の日本です。これを知った時になるほど、と思いました。日本は結局、横断型ではなく縦割りでやってしまった。つまり、社会とのつながりをあまり考えないんです。
(*2)梅棹忠夫(1920-2010年)生態学者。民族学・文化人類学の巨人として知られ、「梅棹文明学」とも称されるユニークな文明論を展開し多方面に多くの影響を与える。登山と探検を愛し、世界中でフィールドワークを展開。その活動を基に数々の著作を残した。

――それが縦割り型教育ゆえの弊害ということでしょうか。
原爆などの兵器を開発したエリートたちもそうだったかもしれませんね。どちらかといえば、社会とのつながりを重視しない雰囲気がある。もしリベラルアーツ型の学問だったら、「自分が作っている火薬が、隣のお姉さんの頭の上に落ちるかもしれない」って想像するはず。でも、薬を作っている人は、やっぱりそうは思えないんだろうなと思う時があるんです。正直に言えば、僕もそうでした。自分が作っている薬が実際にどう人に届くかなんて考えずに、研究室の中だけで完結していたんですが、それって怖いことだなと思うんです。そういうことを伝えたいんですよ。
理系に限ったことではないかもしれませんが、一般的に大学生は、街との接点があまりないケースが多いですよね。僕自身も研究室にいたときは社会のことなんて全然考えなかった。大学のあった仙台市民とのつながりなんてなかったですね。でも、大学4年のとき、弓道一筋だった僕が挫折して、自我が揺らいだ。そのときに薬草園を散歩し始めたんです。そしたら管理している地元のおっちゃんたちと仲良くなって、街とのつながりをはじめて感じたんです。その経験は大きかったですね。
日本における医者の存在は、どこかで作られた仕組みが降臨してきて、「お医者様」となる。それは、いわゆるドイツ型の権力構造の中でできてきたわけですが。でも、チベットでは医者は街の中で育つ。人々に必要とされて育つんです。日本は「医者がどこかで作られて降臨してくる」国家資格型のモデルだけど、チベットの医者は「みんなで支えて育てる」というアーティストみたいな感じ。僕は今、そういう存在になりたいと思っていますね。
――やっと意味が分かってきました。小川さんが、なんでこういうことやってるんだって。
社会とつながり、自然とつながる
この前も、いつも行く温泉で「小川さん、ドクダミ欲しいんだけど」って近所のおじいちゃんに言われました。それで、朝からドクダミを刈って、その人の玄関にバーッと置いてきたんです。「自分で取れよ!」って心の中で毒づきながら(笑)。世間では「チベット医師」って言われているのに、ただの小間使いみたいにドクダミを持って帰ってくる。それがね、我ながら面白いんですよ。おじいちゃんたちとの関わりが。結局、それって社会とのつながりなんですよね。
それと同じように、自然とのつながりもある。僕なんかは山を歩くだけでいつもクマに怯えている。超リアルな自然との利害関係があります。木も伐りますしね。木を伐るときなんて本当に怖い。でもその怖さが大事なんです。大事な講演会があって、すごく緊張するなっていう時は、2、3日前に大木を伐ることがあります。「これを乗り越えたら講演会もいける」みたいな。変な心構えですけどね。でもそういう自然との対峙の中で気持ちを整えています。
――面白い対峙の仕方ですね。
実際は木を伐らなくても講演会はうまくいったかもしれない。でも自分の中では、「何かに怯える感覚」を持っていないとダメなんですよ。「負けるかも」「震えるかも」という感覚をね。特に子どもたちの前で話す時は緊張しますね。早稲田大学で学んでいたとき1年間だけ都内で暮らしていたのですが、東京の安全地帯にいると、自分の言葉がどんどん弱くなるのが分かったんです。積極的に恐怖に対峙していく。つまり、大自然の中で生きる時に、自分からちょっと先手を打ってちょっと危険なことをやっておく。そのほうがいいと感じていますね。
【後編に続く】