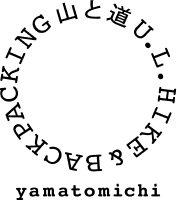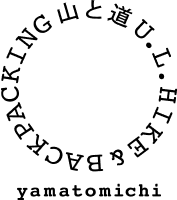山と道HLCディレクターの豊嶋秀樹をホストに、身体行為としてのハイキングをリベラルアーツ(生きるための学問)として捉え、同じく身体行為である「見る」ことや「聞く」こと、「食べる」ことなどを手掛かりに、ハイキングのその先にある価値と可能性を探っていく連載『HIKING AS LIBERAL ARTS』。
#5後編となる今回も、引き続き外国人初のチベット医(アムチ)となった小川康さんを訪ね、私たちの身近にありながら遠い存在である「薬」について話を伺っていく。
薬草で一番大事なのは、それを「見つける力」という小川さん。読み終えた頃には、きっともっと「薬」を身近に感じられるはず。
オルタナティブが実は本質的?
――昔は情報の出所が、大きなメディアや病院など、ひとつのルートしかありませんでした。でも今の時代は、小川さんみたいに薬の話をオルタナティブにしてくれる人もいて、選択肢が広がってきている気がします。
昔は「これが本筋だ」っていう1本の道しかなかったけど、今はちょっと違う道があるんですよね。
――例えば、僕らがやっているULハイキングもそうなんです。以前の登山は、とにかく山頂に立つのが目的で、それ以外は「敗退」として扱われていた。でも「いや、そうじゃない。自然の中に浸って、その場を感じることが大事なんだ」っていう考え方が出てきた。そうなると、重装備じゃなくてもいいし、もっと軽く、顔を上げて歩ける登山ができる。装備だけじゃなくて考え方そのものの変化ですよね。それに共感する人たちも出てきたんです。
なるほど。チベットでも宗教的な理由で聖なる山には登らない。彼らは頂上よりも峠を重視するし、山で普通にピクニックしたり薬草を採ったりする。目的が終われば、無駄に頂上まで行かずに帰る。そういう姿勢があるんですよね。
――登山の歴史を調べても、日本には明治まで登山文化がなかったんです。留学した人がクライミング技術を持ち帰って、それが科学技術と同じ経路で入ってきた。だから「何でも西洋から入ってきたものが正しい」みたいな流れだったけど、今はそうじゃない選択肢もある。鳥を見に山へ行くとか、身近な低山でのピクニックもそれでいいんじゃないかって。
現代医学も同じで、はっきりした「ピーク」だけを薬として認めて、それ以外は排除する。でも薬草はもっと曖昧で、名前がはっきりしないものだって効能がある。そういうオルタナティブな考え方って、実は本質的なんじゃないかと思うんです。
――チベット医学も、いわゆる代替医療とかオルタナティブって括られることが多いですよね。
それが実は嫌なんです。僕がやっているのは「チベットに根付いた本物の医学」であって、サブカルチャー的な代替医療とは違う。現代医学は6年間勉強してやっと一人前になりますよね。でも漢方なんかは、日本では授業にないから「ちょっと学ぶ」くらいの扱いになっている。チベット医学は5年間、毎日10時間近く勉強して、気が狂うほどの努力をして初めて身につく学問。それを、ちょっと資格商売的に「本を読んで学んだ」レベルと同じにされるのは違うんです。
だから「オルタナティブ」という言葉には、正直に言うと違和感があります。学問を身につけるにはどれだけの時間と努力が必要なのか。そういうものを軽く扱わないでほしい。僕としては、医学部のカリキュラムの中にも、もう少し代替医療をうまく取り入れられたらいいのにな、と思っていますが、現実的にはこれ以上、授業を過密にはできないでしょう。

薬草が日本の医学で取り上げられなくなった理由
――今の大学の医学部って、授業の中に東洋医学とか薬草のことって全く出てこないんですか?
「全く」とは言いすぎですが、ほぼないですね。先生が経験談としてサブ的に触れるくらいはありますけど、授業として体系的に教えるわけじゃない。僕は授業で扱うべきだと思うんです。でも、実はもう「時すでに遅し」で、情熱をもって薬草を教えられる人材が少なくなったんですよ。戦後の混乱みたいな状態ですね。だから授業は「ない」と言っていい。医学部の雰囲気としても、薬草に興味を持つこと自体が「隠れキリシタン」みたいな感じになっています。僕が特別授業で呼ばれると、興味を持って来てくれる学生もいるけれど、ちょっと変わった人だと思われてしまう。その空気感が良くないですね。
――どうしてそうなったんでしょう?
理由は近代戦争が考えられます。チベットでは今も薬草が主役。でも日本では戦争を経て薬草が排除されました。最初のきっかけは1877年の西南戦争です。銃火器の戦争になると、薬草じゃ役に立たない。銃弾が体に入ると麻酔と消毒が必須になるからです。西洋医学の始まりはまさに「麻酔と消毒」なので、西南戦争を経て漢方の廃止が決まりました。その後の第一次、第二次世界大戦ではもっと顕著です。戦艦大和にヨモギを積んでも役に立たないですよね。必要だったのは、大量合成された消毒薬や麻酔薬、それに脚気の予防のためのビタミンB群。戦争には薬草が不要とされたわけです。
一方で、チベットは近代戦争を経験していない。だから近代医学の必要性がそもそもなかった。戦争がなければ、大量の重傷者は出ない。つまり近代医学は「戦争があったから必要になった」とも言える。江戸時代レベルの生活なら、大怪我も少なくて、薬草で十分だったんですよ。確かに日本の薬学部には法律で薬草園の設置が義務づけられていて、2003〜2008年の薬学部新設ブームにともなって薬草園が増えました。でも「義務だから一応作った」だけになってしまい、形骸化している薬草園も少なくありません。
また、戦後はアメリカ主導で復興が進んだこともあり、合成化学が重視されました。僕が学んだ東北大学薬学部でも13の分野があって、ヒエラルキーの一番上が有機合成化学。研究費の配分も違いました。逆に生薬学は一番人気のない学問だから「薬草なんて相手にされない」という雰囲気ですね。そんな中で僕が薬草に興味を持ったのは客観的に見ても珍しいと思います。

戦争と医学の関係
――戦争がなければ西洋医学ってここまで普及しなかったということですね。もちろん、いつ戦争が起きるか分からないけれど、今の生活で考えれば、せいぜい交通事故くらいでしょう。日常生活で薬と関わる場面を考えたら、西洋医学じゃないオプションも十分にあると思うんです。
そうですね。戦争に加えて、ひとつ大きな要素として感染症があります。これまで人類を大量に死なせてきたのは、戦争と感染症です。戦争はなくせる可能性があるけど、感染症はまた別問題。ワクチンに関してもまだ結論は出ていないし、ここは別枠で考えるべきでしょう。だから、戦争も感染症もなければ、「合成薬は本当にそこまで必要か?」ということになる。
例えば皮膚の火傷なんかは、重症の場合は別として、紫雲膏という薬草の薬と現代薬の差ってそれほどは出ません。心臓や脳梗塞のようなピンポイントな病気では、もちろん必要で、それ以外の多くはそうでもない。歯の治療は分かりやすく進歩があるけど、逆に「それほど頼らなくてもいい領域」はまあまああるんですよ。これは僕だけじゃなく、みんな薄々気づいていると思います。事実、処方薬の飲み残し問題が顕在化していて、お金に換算すると約500億円にもなると言われています。もしかしたら、日本は潜在的に「戦争の準備」をしているんじゃないかな、なんて意地悪な発想も生まれてしまいますが、もちろんこれはあくまで極論です。実際、2020年のワクチン問題の時も「なんで日本はすぐに作れないんだ」と批判されたけど、あれでもかなり早かったのではないでしょうか。普段から薬を大量合成しているからこそ対応できた。
――なるほど。ゼネコンみたいな話ですね。
そうそう。ゼネコンって悪く言われがちだけど、阪神大震災の後の復興の早さなんかを見ると、普段の公共事業が技術の維持や訓練になっているという見方もできます。年度末の「掘って埋めて」の繰り返しの工事がときに批判対象となりますが、リハーサルと捉えることで、とりあえず納得することができます。
――でも、もし薬草で対応できるなら、薬草を選ぶという選択肢がもっと広まってもいいですよね。
そうなんです。例えば医者が処方するときに「これくらいの風邪なら、自分で葛根湯を作ればいいよ」とか言ってくれたら助かりますよね。ドイツでは医者が普通に薬草(ハーブ)を処方しますし、ちょっとした皮膚病や痒み、痛みなら薬草で十分なんです。だからこそ薬草で補える範囲は広いんです。
オウレンとオウバクが薬草界のツートップ
――薬草の文化は、もっと広まってほしいです。でもお医者さんからは教えてもらえないから、自分で学ぶしかないのかもしれませんね。
そこは難しいですよね。僕は専門的に学んできたから判断できるけど、一般の人には学ぶ機会があまり与えられていない。でも実は、「この薬草さえあれば一番役に立つ」というものがあるんです。
――それは何という薬草ですか?
オウレンです。これは歴史が証明しています。『日本薬学史』(昭和24年初版)という本があるのですが、飛鳥時代からの薬草と薬の歴史が網羅されています。それによると日本の歴史の中で一番多く使われてきた薬草がオウレンであることがわかります。

オウレンの花。根茎が生薬として薬用される。(写真:Adobe Stock)
オウレンには整腸作用や消炎作用、鎮静作用、抗菌作用などがあり、胃腸炎や下痢、湿疹や口内炎などの症状に用いられます。だから人々は日常的にオウレンを摂って、自分の体内の菌を抑えていたわけです。しかもオウレンには頭に昇った血をスッと下げる作用があるんです。しかし、今は上下水道や冷蔵庫が普及したので、生活スタイル的に薬草の出番が減ってしまった。
もうひとつ、オウレンとツートップとも言えるのがオウバクで、今でも探せばそのへんの山にも生えている木です。抗菌作用や消炎作用があるので、整腸剤として使われたり、打ち身や捻挫にもすごく効きますよ。昔の日本では水や食料の腐敗で下痢を起こすことが多かった。だから古い薬の中心はオウレンとオウバクでした。動物性のものでは熊の胆もありましたが、薬草の主役といえばやはりこのふたつです。

オウレンの材料となるキハダの木。名前は樹皮の表皮を剥ぐと黄色の内皮が出てくることから。(写真:Adobe Stock)
オウレンとオウバク、このふたつはどちらも黄色のベルベリンという成分を含んでいます。ベルベリンはドラッグストアに行けば、下痢止めや目薬など、さまざまな製品に使われている優れた成分です。
――それは植物由来なんですか?
もちろん植物由来です。ただし合成も可能ですが、経済的には植物由来の方が安いので基本は植物から抽出されています。ちなみに植物由来でも石油由来でも、分子レベルではまったく同じです。昔は違ったのですが、2001年に野依教授がノーベル賞を受賞した研究で、自然由来と合成の違いがなくなりました。だからといって、「合成の方がいい」というわけではありません。合成の問題は、大量生産が可能になってしまうことにあります。自然の摂理を無視してしまう。でも、もし合成の技術がなければ、たとえばビタミンCは奪い合いになっていたでしょう。実際、今のビタミンCはほぼ合成です。
日本人がまず学ぶべきは、このオウレンとオウバクを見分ける力です*。昔のおじいちゃんやおばあちゃんは詳しいですよね。とにかくこのふたつを見つけられれば、あとは加工方法さえ分かれば薬として使えます。でも、多くの人は「薬草を勉強する=知識やうんちくを覚えること」だと考えてしまう。そうじゃなくて、一番大事なのは「薬草を実際に見つける力」なんです。
*個人でオウレン、オウバクなど医薬品に属する薬草を採取し、個人的に利用する場合は問題がない。ただし、販売すると違法になる。

『森のくすり塾』の庭にも、様々な薬草が生えていた。
――なるほど、それは生き延びるための知恵としてすごくいいですね。
だから食品に属するハーブとかは、飢餓もなく豊かで戦争のない世界でこそ活躍できるものといえます。それはそれとして、僕はサバイバル状況で薬草を医薬品として活かすことを考えています。山で遭難した時にビバークすることになって、豊嶋さんが足首を捻挫したとします。僕がいれば、すぐにこう言えますね。「よし、オウバクを見つけるぞ!」と。オウバクはキハダの樹皮ですから、キハダの木を探しに行くんです。オウバクを見つけたらどうするか。オウバクを細かくして、もし水があればお湯を沸かして、できれば小麦粉を混ぜます。小麦粉がなければおにぎりでもいい。おにぎりを潰して、オウバクの粉を混ぜて、患部に当てて縛る。これで間違いなく効きます。
――土地に根付いてきた薬草の知恵は時代を経るごとに失われているということでしょうか。
以前、兵庫の丹波篠山に講演会に行ったんですよ。丹波と言えば、ブクリョウという薬草とオウレンが古来より有名なんです。その講演会で、「オウレンを知っていますか?」と聞くと、あるおじいちゃんが「ああ、いつも学校から帰ったら、お小遣い稼ぎに掘りに行ったぞ!」って言うんですよ。もう何年も、もう60年も掘ってないな、と。「明日、その場所に連れてってくれませんか?」とお願いしたら、「ああ、いいよ」と言って、山に連れて行ってくれたんです。そしたら、ありました。しかも、そのむかし使っていた特注の小さな鍬まで持ってきてくれて。すごいでしょう? あれが薬草の身体性なんです。「久しぶりだなあ」ってそのおじいちゃんは言うんです。こういうのが僕は嬉しいんですよ。みんなが記憶を呼び起こしてくれる。80歳以上のおじいちゃんたちの記憶を呼び起こすこと、これが薬草文化の復興には一番早い道なんです。小さい頃からやっていたからこその早さというか、日常さというか。そういう身体性が、今の80歳以上のおじいちゃんたちにはギリギリ残っているんですよね。
――今までハイキングで、数多くのオウレンやオウバクの森を通り過ぎてきたと思います。
そうでしょうね。僕の自慢は、オウレンが話しかけてくることなんです。オウレンが僕をほっとかない。なんでだろうね、あれ。不思議なんですけど。

キハダの樹皮からコルク質を取り除き、乾燥させると生薬のオウバク(黄柏)になる。
なぜドクダミやスギナが有名になったのか
――ドクダミやスギナも有名だと思うのですが、これらはどうなんでしょう?
ドクダミやスギナについてですね。僕の見解をはっきり言いますと、これらは劇的には役に立ちません。なぜなら、オウレンやオウバクをプロ野球選手とするなら、ドクダミやスギナはせいぜい高校野球くらいなんです。それぐらいのヒエラルキーがあると思います。ではなぜ、ドクダミやスギナが有名になったのか。それは、オウレンやオウバクといったものが、法律で医薬品として扱われ、専門家しか扱えなくなったことに一因があります。薬草への規制は戦後徐々に厳しくなったのですが、昭和46年に施行された法律で厳密に規制されることになりました。
オウレンやオウバクが製薬会社の専売となったために、食品会社の人たちはドクダミやスギナなど医薬部外品の野草しか取り扱えなくなり、それらを医薬品のように持ち上げて販売しました。たとえば、ドクダミ茶という商品の効果効能を標榜すると薬事法違反ですが、植物としてのドクダミそのものの効能を語るならば表現の自由として当時はギリギリ許されていました。彼らも生き残るために必死だったと思います。厚生省はそうした事情を知りつつも、医療事故が起きないことを前提に、ある程度は寛容な姿勢で対応してきました。
これが、私たちがドクダミやスギナ、ヨモギや柿の葉が、医薬品のように劇的に何かに効くのではないかと思ってしまう理由といえます。薬効的に本来はオウレンやオウバクに及びません。あちらはプロフェッショナルですからね。結局、雑誌や新聞の広告で民衆の目に触れることの多い健康食品はほとんどがアマチュアなんです。そして、医薬学部で薬草が教えられていないがゆえに薬草の専門家が存在せず、結果、誰もが薬草の先生を名乗れるというカオスな状況が生じました。だから薬草の序列を明確にするためにも私は、はっきりとオウレンとオウバクを推します。
――ビワの葉はどうでしょう?
ビワの葉の民間療法については、1970年代の健康書ブーム*が発端となって広まったようです。ただ、ビワの葉茶は江戸時代に京都と江戸で大流行したという実績があります。それは間違いありません。
*1974年創刊の健康雑誌『壮快』(ブティック社)、1976年創刊の健康雑誌『わたしの健康(現在は『健康』)』(主婦の友社)や、1978年発行の東城百合子による著作『自然療法』(あなたと健康社)など。
――ビワの葉を焼酎に漬けて肌に塗ったりしますよね。
それらも健康雑誌などの影響によるものと推察されます。しかし、第一に「害がない」ことが大切ですし、そもそも、当時、化学物質を盲目的に推し進めていた日本社会に於いて、当時の自然派ブームが果たした「ブレーキ」の役割は偉大といっても過言ではありません。
ただし「ビワの葉と癌」についてですが、これは1970年代、アメリカの大ブームに起因していて、アメリカ食品医薬品局(FDA)が根拠のあるデータを提示して否定したことでブームは収束しています。それが日本に伝わって時間差でブームになったという経緯を私は知っているので、冷静にコメントすることができます。
ただ、江戸時代にビワの葉茶(枇杷葉湯)が広まっていたのは間違いないです。夏の熱や食中毒、熱中症の予防として当時飲まれていたものです。ですから、私はビワの葉茶はお勧めします。スギナ茶のブームも健康雑誌での特集の影響だと考えられ、もともとはドイツの民間療法にヒントを得たのであって、けっして日本の民間療法ではありません。
昔のおじいちゃんたちがスギナを生活に取り入れていたという記録はありませんし、耳にしたことはありません。考えてみてください、土地に根付いたおじいちゃんやおばあちゃんたちが実践していないことは、おおよそ、もともとの日本の文化にはなかったことなんですよ。

ビワは果実が食用される他、葉はお茶として利用される。(写真:Adobe Stock)
――僕が暮らす北海道の山で見つけられるカバノアナタケは、白樺のウロにある固いキノコの一種で、煎じて飲むと良いと言われてるんです。春スキーをしながら探したりするんですけど、効果はどうなんでしょう?
効果を言語化するのは、とても大変なことなんです。なぜなら、今「エビデンス」という言葉があるでしょう。実は、このエビデンスという言葉は日本では1990年代以前にはほとんど使われていませんでした。昔はなかった言葉が、いつの間にか昔からあるように思われています。エビデンスが厳しく求められるようになった1990年以降、臨床試験の母数も、昔とは桁違いに増えました。昔のまだ雑だった時代と、今のようにどんどん厳しくなっている時代とで、薬草が何に効くか語ろうとすると、どのレベルの試験で言っているのかという話になってくるんですよ。その結果、言葉の重みも変わってきました。昔は言えても、今は言えなくなってきている薬草の効能もたくさんあります。その是非はともかく、動物実験や人体実験をしてデータを積み重ねているので、言葉の重みが違うんです。
「ディープルッキング」で薬草も見えてくる
――昔は、小川さんが研究していたような原子や電子のレベルのことは分からなかったということですね。
そう、昔は薬草が最後の原子のようなものだったんです。一番の最小単位でした。でも今は、薬草よりもはるかに小さい単位のものが分かっています。それを知りながら、昔の価値観で薬草を語ろうとしても、話が通じないんですよね。だから、「これが何に効くか?」と聞かれても、自信を持って答えることはできません。ただ、それを飲んで癌が治ったという個人例はあるかもしれない。それはそれでいいんです。でも、今のエビデンスが求められる世の中では、それは個人の体験にすぎません。本当にそれで治ったのかも分からないし、そういう人はきっと、他にもいろんなことを試しています。生活習慣も含めて、ひとつのことだけが原因とは言い切れないんです。
でも、歩いているだけで薬草に気づくことはできます。例えば、石川県の白山比咩神社の参道に行くと、両脇に薬草がたくさん生えています。葉っぱだけでは地味でなかなか分からないんですが、私は薬草に関してだけは「ディープルッキング*」をしてきました。チベットで生死をかけて山に入って薬草を採ってきたことで、この能力が宿ったようです。昔の日本人には、こういう能力を持った人がもっと多かったと思います。
*本連載の第1回目に登場したロジャー・マクドナルドさんによる著作が「DEEP LOOKING」(AIT Press)。「アート作品を観察する」という行為を深く瞑想するための有力な手段として再発見し、この危機の時代に適応するための重要なテクニックとしても活用できるものとして提案している。

『森のくすり塾』の薬草畑
――ディープルッキングすることで薬草も見えてくるんですね。
その反面、僕は現代アートの美術館に行っても、さっぱり分かりません。見る訓練をしていないからです。同じように、薬草に関しても見る訓練をしていないから、分からないだけなんです。だからぜひ、薬草園などに足を運んで、じっと見てみてください。薬草園はまさに博物館と同じで、ディープ・ルッキングする場です。普段から見続けていると、不思議と分かるようになる。身近に薬草園がない場所でも、ちょっと里山に出かけて探せば見つかります。僕は店舗の駐車場に植わっているキハダを毎日見ています。自分で植えた木は、やはり気になるものです。オウレンも僕のところに集まってきます。出会った人が「小川さん、フジバカマもいる? ヤクモソウもあげるよ」と声をかけてくれるんです。
植えておくと、毎日見ているから、それがなんだか分かるようになる。車を運転していても、「道端に何かある」と気づくようになるんです。それぞれの専門分野の人たちには、そういう特殊能力のようなものがあるでしょう。私はたまたま、それが薬草に関してあるというだけです。

「森のくすり塾」の駐車場に生えているキハダ。
――ハイカーや登山者など、山に行く人たちが薬草の知識を知っていたら、もしもの時にも助かりますよね。
まさにそうなんです。だから災害マップに「ここにオウレンがある」と載せたり、公民館や小学校にヒマラヤスギではなくキハダを植えておくべきだと思うんです。9月1日の防災訓練でキハダの使い方を教えるとかね。
災害時には感染症が広まります。2024年の能登半島地震は冬でしたが、夏だったらもっと下痢などが広まっていたでしょう。もちろん、抗生物質を飲むのが一番ですが、もしすぐに入手できなければオウレンの出番だと思ってほしい。そうしたときに、土地に根ざしたおじいちゃんたちが活躍するんです。「おじいちゃん、どこにオウレンがあるか知ってる?」と聞けば、「ああ、採ってきてやるわ」と山に行ってくれる。かっこいいでしょう。オウレンを採ってきて、みんなで煎じて飲めば、災害時であっても、少しは前向きになれるんじゃないでしょうか。
薬草の知恵を途絶えさせないために
――あるものでなんとかする、という知恵ですね。わざわざ取り寄せたり、遠くから掻き集めてきたりするのではなく、そこにあるもので本来の目的が果たせるのに、それを見る目がなかったり、知らなかったり、気づかなかったりすることで、遠回りしてしまう。
日本では食料の国内自給率の重要性は認識されているのに、薬草に関してはそうではないですよね。例えばキハダは日本にもかなりありますが、自給率はほぼゼロです。人件費の問題で、すべて中国から輸入しています。オウレンはかろうじて最後の砦として、自給率を保っています。また、日本には全国でこんなにヨモギが自生しているのに、誰も採りません。その結果、今では自給率がどんどん下がって、ネパールからの輸入を考えています。なぜそうなったかというと、もともと薬草採集は小学生の課外学習や、ご老人たちの報酬度外視のボランティア活動で成り立ってきたのですが、それらの伝統が途切れようとしていることにあります。
薬草採集は、報酬を度外視した文化として受け継がれてきた側面があります。それが今、時給計算になってしまったのです。「この値段では続けられない」と言っている薬草を採っていたおばあちゃんたちの気持ちは分かります。そういった現場を知っている地域の人たちが、なんとか薬草の知恵をつないでいる状況です。しかし、コロナで小学生の課外学習が減り、一気に状況が変わってしまいました。このままでは国産のヨモギを使った草餅もなくなっていくでしょう。でも、なくなったら自分で作ればいいんです。それだけの話だとも言えます。
とにかく、日本にずっと息づいてきた薬草の知恵は途絶えさせてはいけないと思うのです。できるならば、子どもたちが使う「ジャポニカ学習帳」の表紙は、薬草にすべきですね! 彼らが生き抜くためのサバイバル術のヒントとして、オウレンやキハダ、ムラサキ、センブリなど、そういう薬草の写真を載せたらいいですね。毎日のように薬草の姿を眺めていたら、子どもたちにも、身近な自然の中でも見つける力が必ず身に付くはずです。

小川さんの話を聞いて:豊嶋秀樹
この取材が、小川さんと彼の活動とに再会の場を与えてくれたことをとても嬉しく思う。13年前の小川さんはまだ別の場所に住んでいて、いま『森のくすり塾』がある場所へ僕を案内してくれ、これからの活動について話してくれた。今回再訪してみて、その時に話してくれたいろいろな計画が、長い時間をかけて着々と実現されていることを感じた。『森のくすり塾』は、取材で小川さんが話してくれたことを表現している場なのだ。
僕の父親は小さな町の病院に勤務していたので、子供の頃から僕の家には父が病院から持ち帰ってくる薬で溢れていた。
病気がちだった僕が熱を出すたびに、家に常備されてた「ケフレックス」という抗生物質と「PL」という解熱剤を与えられていた。アトピーの症状があった頃には「リンデロン」、蕁麻疹がでた時には「ポララミン」と大抵の薬は処方薬名で覚えた。その育ちのせいで僕は、「薬」に対する忌避や抵抗の感情のない、素直な患者として大人になった。お陰様で、その影響で後に体調が変化したということには今のところ繋がってはいない。
それほど身近な存在だった薬だが、自分自身の食や働き方などを含めた生活スタイルの変化に伴い、「あんなに薬ばかり摂っていたけど、大丈夫なのだろうか?」という疑問が何かの拍子で持ち上がる機会が増えていった。今回の小川さんとの再会はそんなタイミングのことだった。
「葛根湯」の話は、合成薬しか知らない僕にとっては何度聞いても目から鱗の話である。
「腑に落ちる」とはどういうことなのか、という問いに対して、「原因と結果が1対1の関係のことだ」と小川さんは答えた。現代社会では、言葉で簡単に理解できることが常に求められている。原因と結果が複雑に絡み合う複雑系では「腑に落ちる」答えは有効ではない。
「身体の声が聴けていない状態。そうならないためにも、普段からトレーニングをして、自分の体の声に耳を澄ませることが大切」これはまさに、この連載の目的である。
「自分の中では、『何かに怯える感覚』を持っていないとダメなんですよ。積極的に恐怖を手に入れる。つまり、大自然の中で生きる時に、自分からちょっと先手を打って危険なことをやっておく」という話では、都市での社会生活の中でわかっているようでもつい、鈍感に、そして傲慢になっている僕には少々耳が痛かった。
後編に入ると、「江戸時代レベルの生活なら、大怪我も少なくて、薬草で十分だった。」という話があった。火薬ができてから大怪我のレベルが飛躍し、薬草では追いつかないようなことが多くなったということだ。これは、原発の問題にもつながっているように聞こえた。江戸時代の生活には原発はいらない。
「オルタナティブな考え方って、実は本質的なんじゃないかと思うんです」という小川さんの言説は、非常に思慮深いものだった。時代が移ればそれまでのオルタナティブが常識となる。
つい本文からの引用で、あれもこれもと語りたくなってしまう。ほどほどにしよう。最後にもうひとつだけ。
「多くの人は『薬草を勉強する=知識やうんちくを覚えること』だと考えてしまう。そうじゃなくて、一番大事なのは薬草を実際に見つける力なんです」
これは、まさにULハイキングそのものだ。理屈やスペックを読み知ることも興味深いが、自分で歩いて学んだことを身体性をともなって蓄積していくことが本当に大切で面白いことなのだろう。
そういうわけで、これからのハイキングには「オウレン」と「オウバク」の画像をスマホのホーム画面にしておくことをオススメしておく。
小川さん、ありがとうございました。まだまだ聞きたいことがたくさんあります。次は『森のくすり塾』にワークショップを受けに行かせてください。