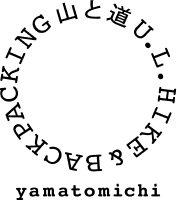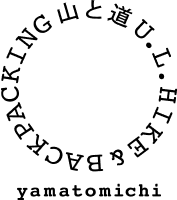山と道というこの奇妙な山道具メーカーの特徴のひとつは、アウトドアの文脈だけには収まりきらない、実に様々なバックグラウンドを持つ人々との関わりがあることかもしれない。
この『人・山・道 -ULを感じる生き方-』では、そんな山と道の様々な活動を通じて繋がっている大切な友人たちを訪ね、彼らのライフや思考を聞いていく。一見、多種多様な彼らに共通点があるとするならば、自ら背負うものを決め、自分の道を歩くその生き方に、ULハイキングのエッセンスやフィーリングを感じること。
#8となる今回は、山と道のローカルでもある鎌倉を拠点に活動を続ける「イマジン盆踊り部」…通称「盆部」から、代表の大嶋櫻子さん、副代表の瀬能笛里子さん、歌い手の山口愛さんに話を伺った。
生歌、生バンドで音頭を演奏し、踊り子も含めたメンバーは現在総勢40名以上。ひとたび演奏と踊りを始めれば、そこを祝祭の空間としてしまう盆部。『山道祭』にも、2019年の初回から祭りの欠かせない要素として出演し、毎回、会場を笑顔と踊りの坩堝にしてもらっている。
「盆踊りで平和の輪を描く」をテーマに活動を続ける彼ら、彼女らのバックストーリーと、未来に繋ぎたいものとは。
盆踊りが生み出す輪
ぐるぐると輪を描き、集団が同じ振り付けで踊りながら進む。はじめてイマジン盆踊り部がつくる盆踊りの場を体感したのは、熱帯夜が続く真夏の鎌倉の小さな広場だった。
バンドによる生演奏の音が体の奥まで響く中、見知らぬ人同士がひとつの輪になって踊る。踊りながら、やがて心地よく、心が穏やかになっていくような、初めての感覚が訪れたことを思い出す。
日本に暮らし、幼い頃から盆踊りに触れてはきたが、盆踊りをしっかりと意識し、その魅力に衝撃を受けた瞬間だった。

8月に江ノ島で行われた盆部自主企画の盆踊り大会『発酵盆祭2025』の様子
盆踊りのルーツ、念仏踊りのふるさとで
鎌倉を拠点に、盆踊りを通して人とつながり、平和の輪を広げているグループが「イマジン盆踊り部」、通称「盆部」だ。
「盆部は、人生を“盆に振った”人たちの集合体なんです」
盆部を創立したメンバーの瀬能笛里子(ふえりこ)さんはそう話す。盆踊りに魅せられ、盆踊りの可能性を信じて広げている盆部の活動は、原発反対のメッセージを伝える社会活動から始まった。
2011年の東日本大震災と、それに続く原発事故。その後の社会の空気の中で、神奈川県の湘南地域で「イマジン原発のない未来かまくらパレード」というデモが定期的に行われていた。このデモを主催していた団体が、笛里子さんが代表を務めたことがある「イマジン原発のない未来kamakura parade」。デモを「パレード」と呼び、誰もが参加できる雰囲気をつくり、多くの人の賛同を得た。
「原発の問題に対して、真っ向から反対と訴えても反感を得るだけなので、パレードをして、なんだかあの人たち楽しそうだな! と感じてもらえればと思いました。同じ思いの人たちがこんなに町にいるよ、私たちはこういう未来を描きたいよねということを表現するパレードでした」と笛里子さんは話す。

盆部副代表の瀬能笛里子さん
そのパレードの表現方法のひとつとして、盆踊りをしようという話が持ち上がる。大きな転機は2012年9月、神奈川県藤沢市にある遊行寺でのパレードだった。
その時はまだバンド編成ではなく、ピアニカやカスタネットで録音した音源を流しながらの行列踊り。曲は「東京音頭」を替え歌にした「イマジン音頭」のみだったが、この行列踊りは大きな反響を呼んだ。

2012年、藤沢の遊行寺を目指して行われたパレード。

2013年鎌倉での冬のパレード。
行列踊りの終着点となった遊行寺は、盆踊りのルーツといわれる「踊り念仏」が伝わる地。約700年前に一遍上人が藤沢の片瀬で踊り、全国に広めた「踊り念仏」が盆踊りになっていったと考えられているのだ。
「その時のパレードは、なんだか、一遍上人に踊らされて遊行寺まで辿り着いたみたいな印象でしたね」
そのパレードに飛び入りで参加したことをきっかけにメンバーになった大嶋櫻子さんは当時をこう語る。
「知り合いがいるわけでもないのにイマジン音頭に参加してみたんです。1時間半ほどを一緒に踊った後に、『ああ、もっと踊りたいな』という思いが心の奥底から沸き上がってきました」
こうして、「イマジン原発のない未来」から派生する形で、盆踊り好きが集うことで「イマジン盆踊り部」の誕生につながっていった。

イマジン盆踊り部代表の大嶋櫻子さん。後はベース担当の吉田至宏さん。
人生を盆に振った人たち
「人生を盆踊りで、盆に振りました」
冗談めかして語られるこの言葉だが、彼女たちの生き方の本質や、盆踊りが持つ不思議な引力の強さを表しているようだ。
結成以来、盆部の活動の輪は、盆踊りの輪のように広がり続け、現在では、全ての踊り子を含めると40名ほどがメンバーに名を連ねる。当初は純粋に盆踊りを踊ったり研究する、正に「部活」として始まった盆部だったが、盆踊りの楽しさをどう伝えるかを考え、バンドを結成することに。
「バンドの生演奏の力があれば、もっと多くの人を踊りの輪に引き込めるよね! って皆で話したんです。そして、CDアルバムを作って、そのCDが、私たちがいないところでも盆踊りの熱量を伝え、各地で盆踊りの場ができていったらいいね、という目標ができたんです」櫻子さんはそう振り返る。
そんな時に、別の民謡ユニットを組んで活動していたボーカルの山口愛さんとの出会いがあった。キューバやベネズエラでの活動の経験を経て日本の民謡の面白さに目覚めた愛さんだったが、バンド入りを誘われた当時は、盆踊りは炭坑節と東京音頭しか歌えなかったという。

盆部歌い手の山口愛さん。
愛さんが加入したことで、アルバム制作は急ピッチで進んだ。そんな中で生まれたのが、盆部の代表曲のひとつ「発酵盆唄」だ。千葉県香取郡神埼町で江戸時代から続く酒蔵である『寺田本家』にて毎年3月に行われる「お蔵フェスタ」で、盆踊りを行うことになったことから、酒作りとは切っても切り離せない「発酵」をテーマにした曲を制作したのだ。
盆部の活動は、こうして特定の場所やコミュニティと深く結びついて展開していくのも大きな特徴だ。自らの主催イベントも行うが、それ以上に、縁があって呼んでもらえる場所に赴いたり、盆部の踊りを体験した人が「自分が暮らす街でもやりたい」と地元で祭りを立ち上げたりするケースが多い。
「盆踊りを体験した人が自分のところでもやりたいと言って、人を集め、時間をかけて練り上げ、準備して私たちを呼んでくれるんです」と笛里子さん。熱量が熱量を呼び、火種が各地に飛び火していくのだ。

『発酵盆祭2025』でも踊りの輪が何周も生まれ、大きな一体感に包まれた。
利己ではなく利他。そして、手放すこと
盆部が生み出す踊りの輪には、体験した者でなければ分からない特別な空気がある。それは一般的な音楽ライブとは根本的に異なる。
「いわゆるライブって、お客さんがステージ側の演者を見てもらう感じになると思いますが、盆踊りでは演者をほとんど見ていません。それが盆踊りならではの演者とお客さんの関係なんです」と愛さんは話す。
盆踊りでは、演奏者や踊り子が主役ではない。盆踊りの輪そのものが主役なのだ。盆部は表現者でありながら、利己ではなく利他。自分を前に出すのではなく、自分という存在を手放し、その場に集う人や空気と調和する。そこには、軽やかに削ぎ落とされた生き方があるように感じた。
「盆踊りに関わるようになって感じるのは、人と調和するからこそ、いろんなことに巻き込まれもするけど、自分にとって本質的に何を大事にしたいかがよく見えてきて、 自分の暮らしが整うことがあるんです」と櫻子さん。それは、軽量化を通じて自分にとって本当に必要なものは何かを見出す、ウルトラライトハイキングの理念にも通じる部分だ。
自分を手放すことで踊りの輪は大きくうねり、調和と本当に必要なものをもたらしてくれる。

『発酵盆祭2025』でのステージ。
輪がもたらす調和
「盆踊りの輪にいる人たちは、みんな笑顔になるんです」と笛里子さん。確かに盆部がつくる空間では、踊りの輪にいる人も輪の外にいる人も、皆が微笑んでいるのが印象的だ。櫻子さんはこう話す。
「輪の外でただ見守っていた人たちが、ふとした瞬間に巻き込まれて輪の中に入って踊りだすことがあるのですが、そんな時は嬉しいですね。よし! って思う。とうとう来たな〜みたいな」
盆踊りの輪の中に入ると、理屈抜きに、大きなうねりに同調するような身体感覚が訪れる。初めて会った人たちで手をつなぎ、笑顔になる不思議さ。この一体感の秘密は、盆踊りの振り付けの「型」にあるという。
「皆で一緒に踊ることができる盆踊りの振り付けの型が、大きなポイントなんです。型のおかげで、踊りのうまい下手ということは関係なく、ただ踊るだけでそこにいる人同士が同調していくことができるんです」と笛里子さん。振り付けの多くは少しの練習で覚えられ、輪になって踊ることで人々がつながり、大調和が生まれる。そして、音楽と踊りが完全にシンクロしていなくても、不思議と調和するのだ。
民謡は4拍子ではない変拍子も多く、世界各地に輪踊り(サークルダンス)は存在するが、こんなに複雑なリズムを大勢の人で一緒に踊る行為は日本特有のものなのだそうだ。さらに、その型や歌詞は土地と固く結びついていることも、民謡や盆踊りの大きな特徴なのだそう。愛さんはこう話す。

「地域によっては踊りの足の運びが星の並びになっていたり、ちょっと呪術的な意味があったりとか、踊りで土地の神様を目覚めさせるみたいな意味合いがある地域とかもあります。振り付けには船を漕ぐ動作や手作業のリズムが、歌詞にはその土地の気候や労働の苦楽や色恋沙汰が織り込まれているのも面白いですよね」
だが、そんな日本各地の土地固有の盆踊りは今、消滅の危機にあるという。例えば、鎌倉市内でも長谷という地域に『長谷音頭』という固有の盆踊りがあるのだが、練習を長谷以外でやってはいけないというしきたりがあるという。
同じように、外部の人間には伝承しないという習わしのある地域が多く、その昔は、各町ごとに各町の音頭があるほど豊かだった盆踊りの文化はなかなか継承されていないのだそうだ。
日本における盆踊り文化に多く触れてきたことで知った現状。失われゆこうとしている文化の豊かさをつないでいく活動も、盆部が自らに課した使命でもある。
盆踊りはコミュニティを活性化する
盆踊りは世代や立場を超えて人と人をつなぐ力を持つ。例えば移住者にとっては、盆踊りを通して地元の人と話したり、踊りの振り付けの掛け合いをしたりするうちに、コミュニティに溶け込めたりする。この「つなげる力」が顕著に現れたのが、2024年に起きた能登半島地震の支援活動での経験がある。
盆部のメンバーが支援活動で訪れた石川県珠洲市の避難所が、偶然「砂取節」という塩焚きの音頭の発祥地だった。土地のおじいちゃん、おばあちゃんに「砂取節」の歌と踊りを教えてもらい、次の訪問時に習った歌と踊りを披露すると、地元の人々が一緒に踊り出してくれたそうだ。
「歌や踊りは垣根を越えるツールになるんだなと、その時に実感しました」と愛さん。この出来事もきっかけのひとつになり、担い手不足のため前年に途絶えていた地域の祭りも実現した。「砂取節」を歌える人が減っていたのだが、避難所にいる人々が地震以降散り散りになっていた地域の仲間を呼び戻し、祭りの場で、皆で「砂取節」を歌い、踊ることができたのだ。櫻子さんはこう語る。
「祭りはひとりじゃできないんです。つながりがないとできないから、どうしたって地域の人とつながることになるんです」

『発酵盆祭2025』には老若男女の様々な人々が集まっていた。
帰ってこられる場としての盆踊りの輪
盆部が生み出す輪は、国境さえも越えようとしていて、現在、朝鮮半島の38度線にある平和公園で現地に伝わる踊りと一緒に何かをできないかという話も進んでいる。
そんな活動の原点には、「こうありたいっていうものを自分たちで作っていく」 というメンバー皆の共通した思いがある。そして、盆踊りという行為そのものが、彼女たちの哲学と密接に結びついているのだ。
「土地や地域とつながりやすくなる最強のコミュニケーションツールなんです」
そう語る笛里子さんは、盆踊りに果てしない可能性を感じているという。盆部には「これができたら達成」ということもなく、彼女たちがいなくなった後にも続いていくことを願っているという。櫻子さんもこう語る。
「死んだ後に盆踊りの輪がなかったら、私たちがどこに帰ってきたらいいかわかんなくなっちゃうから、ちゃんと次世代にもつないでいくような、盆踊りっていう文化が残っていくようにしたいですね。盆踊りは本来、お盆に帰ってくる亡くなった人をもてなすためのものだから、あの世に行っても帰ってこられる、安心できる輪があるっていうのは幸せなことです」
「見えているものだけが全てじゃないっていう感覚を、盆踊りを通して肌感覚で感じることもできるのです」笛里子さんもそう話す。

『発酵盆祭2025』の縁日で遊ぶ子供たち。
バトンを渡して、次世代につなぐこと
彼女たちは「バトンを渡す」ことを強く意識する。笛里子さんはこう語る。
「盆部があることで祭りが成立するっていうふうには思ってほしくないなと、いつも思っています。その地域の人がどういうふうにして、祭りでおこった火種を受け継ぎ、バトンを渡していくかが大切なことだと思います。そのきっかけとなる盆踊りが楽しいっていうことを知ってもらえるために、私たちは各地に出かけて行くのです」
自分たちが主役なのではない。主役はあくまでその土地の人々と文化だ。イマジン盆踊り部の盆踊りを体感した地域の人の中には、「来年は自分たちでやります」と言って、独自のやり方で祭りを継続していくことも多いそうだ。
「ただ呼ばれた場所に行って演奏するという、バンドの興行的なものとはまったく違うのかもしれません。 一緒に祭りをつくっているぐらいの並走感で、その地域に関わっているのかなって思いますね」 と櫻子さん。
盆部が生み出す踊りの輪は、生と死、過去と未来、土地と人を編み上げる、大きなタペストリーのようだ。時にバラバラになっていた人々の心をつなぎ、災害時には生きる希望となる。土地の記憶と縁を拾い集め、音と踊りに変え、次世代へバトンを渡す。自分たちを手放し、皆で作る調和の輪。
「盆踊りで世界平和の輪を描く」ことを目指すイマジン盆踊り部は、これからも膨らみ、発酵していく。

東日本大震災を受け始まったパレードより2012年に派生した盆踊り集団。NOではなく、自分たちの描きたい未来を盆踊りで表現しはじめる。生歌生演奏の盆踊りは唯一無二で、様々な隔たりがあったとしても手を繋ぎ輪になれば、笑顔になってしまう。そんな奇跡的瞬間を描くことができるならばと日本全国駆け巡る姿はまるで龍のよう。4歳から70代まで約40名で構成された、多種多様な生業をもつメンバーは、趣味思考がバラバラであっても、盆踊りとあらば一丸となる。その事実から、盆踊りで世界平和がつくれると確信している。
インスタグラム