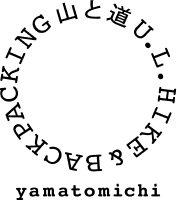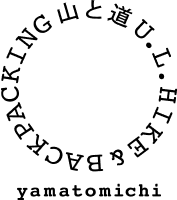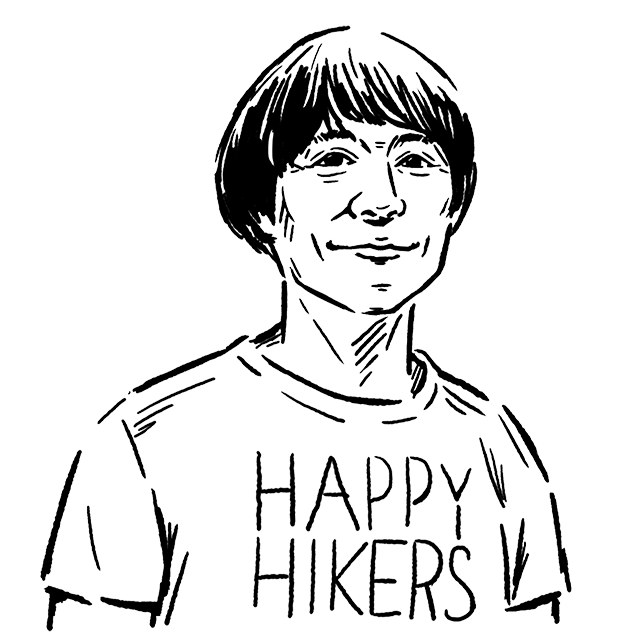2017年の6月から10月にかけて、山と道は現代美術のフィールドを中心に幅広い活動を行う豊嶋秀樹と共に、トークイベントとポップアップショップを組み合わせて日本中を駆け巡るツアー『HIKE / LIFE / COMMUNITY』を行いました。
北は北海道から南は鹿児島まで、毎回その土地に所縁のあるゲストスピーカーをお迎えしてお話しを伺い、地元のハイカーやお客様と交流した『HIKE / LIFE / COMMUNITY』とは、いったい何だったのか? この『HIKE / LIFE / COMMUNITY TOUR 2017 REMINISCENCE(=回想録)』で、各会場のゲストスピーカーの方々に豊嶋秀樹が収録していたインタビューを通じて振り返っていきます。
全国をまわり、ついに山と道のローカルである鎌倉に帰ってきた今回のゲストは、この山と道JOURNALSでもおなじみの東京都三鷹市のハイカーズデポ店主にして日本のウルトラライト(UL)ハイキングの伝道師、土屋智哉さんです。
00年代に土屋さんをはじめとしたごく狭いコミュニティに始まった日本のULカルチャーも15年以上がたち、よくも悪くもシーンが成熟してきた中にあって、「初期にあった実験精神やラディカルさを取り戻したい」と語る土屋さん。
20年近くに渡って日本にULハイキングの種を撒き続けてきた土屋さんから見える、日本のULの現在地とは?

ハイキングはダサいもの

写真:豊嶋秀樹
さて、ついにこの旅の起点であり終点である鎌倉へ戻ってきた。
旅の終わりは雨だった。朝からかなり強く降り続いている。今日のHLCの会場は、東日本編の時と同じ、鎌倉にある山と道の工房兼事務所からはすぐ近く(当時)の大町会館だ。細い路地の奥まったところにたたずむ、ただでさえ昭和的な風情のある建物は、雨の中でいっそう古めかしく見えた。
感傷的な外の雰囲気とは対照的に、館内では会場となる大広間に敷かれた座布団に座る参加者たちが、それぞれに自由な感じで開演までの時間を楽しんでいた。鎌倉は山と道にとってのローカルであることを、参加者同士の打ち解けた雰囲気からも強く感じた。
「僕がやってきたコミュニティーの作り方って、ゆるく集めて、どんどんアメーバみたいに分離拡散させる方法だと思うんですよ。強固なコミュニティーというよりは、ゆるいコミュニティーで、孫のコミュニティーが勝手に育つみたいな。」
僕は、事前にトークの打ち合わせも兼ねて三鷹のハイカーズデポへうかがい、今日の一人目の登壇者である土屋智哉さんに少し時間を取ってもらって話を聞いた。
「東京の場合、いろんなお客さんが来るから、常連しか来ないっていう狭いコミュニティーにはしたくなかったんですよね。育てていくというか、ゆるくて自然に広がるコミュニティー方が良いのかなって思って。逆に今はちょっと変わってきて、どっちかっていうと、狭くて根の深い、ある特定のテーマに対してのコミュニティーっていうものを作っていきたいって思ってる。例えば、完全にロングディスタンスハイカーのためのコミュニティーを作るとか、トレイルとのコミュニケーションを密にして、そこのコミュニティーに入っていくとか。そういう方向性を意識してる。」
土屋さんは、店のカウンター越しに、親しみのある独特な調子で僕にそう話した。
「この店をやっていて一番嬉しかったことは、日本におけるウルトラライトハイキングや、ハイキングカルチャーのムーブメントの突端を作ることができたことだと思う。大げさに聞こえるかもしれないけれど、大きなコミュニティーに繋がってゆく流れのスタート地点でアクションを起こせたのは、自分の仕事の中で一番誇って良いことじゃないかなって、今はすごく思ってる。それは、少数だけど確実にいたハイカーのコミュニティーに支えられたことでもあった。10年以上もこうして店をやってこれたっていうのは単純にとても嬉しいことだし、そこからいろんなつながりが見えてきた。ハイクでつながったコミュニティーが、実は違うレイヤーでもちゃんとつながってたりとか。」
「ハイキング」という言葉から、そこからつながる世界への可能性と広がりを僕は感じる。偏った見方かもしれないが、「ハイキング」は、「登山」には動かなかった他のカルチャーの人たちを反応させる響きがあるように思う。実際、僕にとって「ハイキング」は、「アート」と同義とまでは言わずとも似た色彩を帯びた言葉として聞こえる。
「言葉ってすごく大事ですね。僕が『ウルトラライトハイキングの店』とか、『ハイカー』って言葉を使ったのはかなり意識的なんです。それまでは、世間で『ハイキングはダサいもの』っていうイメージがあったと思うけど、あえて『ハイキング』って呼ぶことで、違う価値観やつながりを作れるんじゃないかって思った。何より『ハイカー』って、響きが良かったんですよね。僕のハイキング仲間たちが『ハイカー』って言葉を自信を持って使っているのを見てたから、やっぱりこの言葉で良いんだって思ったりね。だから、『ハイキング』『ハイカー』って言葉が、こんなに定着したこともすごく嬉しい。」
確かに、「ウルトラライト」という言葉が頭に着く前と後では、「ハイキング」という言葉が与える印象は大きく変わった。それまで、重い荷物に喘ぎながらの縦走登山に限界を感じていた僕に、未来を与えてくれたのも「ハイキング」だった。山を歩くようになる前からの友人だった山と道の夏目くんが、僕にULハイキングのイロハを指南してくれた。その結果、僕の山のスタイルはガラッと変わり、人生への向き合い方も大きな変化を与えられた。
「この店でやってきたこと、発信してきたことも、僕ひとりでやってきたというよりは、僕の周りにいるたくさんの人たちからいろんな影響を受けているんです。だからお店は、彼らが思っていることを発信するための窓口になれれば良いなって思います。」
土屋さんは、白髪混じりのフサフサとした髭を撫でながらそう言った。

東京都三鷹市にあるハイカーズデポのエントランス。 写真:豊嶋秀樹
実験感覚でやれること
「『自分はハイカーだ』っていう人は増えたと思いますね。でも、そこまで軽量化にはこだわってないっていう人が多くなって、『自分はULハイカーだ』って胸を張って言える人は逆に減ったかもしれない。それはそれで別に良いことかもしれないけど、ただ、個人的には、うちのやり方も含めてぬるくなっているなって気がする。だから、今後はちょっとガチガチなところもやっていきたいと思ってる。『4キロとかじゃないでしょ、2キロ切ろうぜ』っていうのとかね。バカなことをしたいって思うようになってきた。」
僕の目をじっと見て話す土屋さんの声のトーンがひとつ高くなった。
「初めた頃は、もっと軽さに対して愚直だったんだよね。軽さでやれることっていうのを少しずつでも拡げていこうって気持ちで。でも、店をやって、ULのことを知ってもらう部分で安全マージンをとったものを提案していくことになっていった。でも、それをおもしろくないと思う自分もいるんですよ。『これ使えるのかな?』って思いながら実験してみることがなくなった。大丈夫かどうかなんてわからないから使うのが楽しかった時代もあった。そういう実験精神を、初心に帰るって意味でもあらためて出していきたいなって思う。『使えるのかどうか、そんなの聞くなや、試してみればええやん』って。」
そう言って、土屋さんは笑った。
僕は、土屋さんのその言葉を聞けたことが嬉しかった。そもそものULハイキングには先鋭的なカウンターカルチャーとしての側面があったはずだと僕は思っている。00年代前半のULの黎明期には、当時のラディカルな連中が、こことは違う世界を作っていきたい、新しい価値で自分たちは生きていきたい、オルタナティヴなライフスタイルを作っていくんだという態度があったはずだと。時間がたち、こうして一般化され、みんなのものになったのは良いことだけど、ULハイキングは今もそういうヤツらの居所でもあってほしいと、僕はパイオニアに対する憧れにも似た気持ちで強く思う。
「『北アルプスで使えないとダメ』みたいな風潮があると思うんですよ。でも、そんなのどうでも良いじゃんって思う。北アルプスで使えるか使えないかは価値判断の基準じゃないよって。だって、『奥多摩、奥秩父しか行かないし!』っていうスタンスももちろんアリだし、僕のULハイキングもそこから始まった。だからもう1回、そのときの実験感覚でやれることをやりたい。『いけるかな、うん、もう少しいけるかも』って少しづつ進んでいったときのように。」
ULハイキングといえば、もうひとつ、当時は製品として世になかったものを自分で作る「MYOG(Make Your Own Gear)」というカルチャーと切り離せない関係で成長していったと言えるだろう。山での生活道具であるアルコールストーブを自分でつくってみることには、「自分の生活をセルフビルドしているというような興奮があった」と、土屋さんは鎌倉でのトークで語った。今では、空き缶を集めてわざわざ自分で作らなくても、ショップやネットで十分に軽量な道具が一式揃うようになった。
「保守的すぎるとつまらないし、ラディカルすぎると広がってはいかない。面白いって思ったことを広めようとするとある程度保守的にならないとうまくいかない。難しいけど、ここのバランスだよね。お店では保守的でいても、自分がラディカルにやることに関しては、責任も持たないし、別に真似しなくて良いよ、でも俺はやるよって感じでね。」
土屋さんの話すラディカルな世界観は、たとえ同じことができなくても、僕たちが歩き続けるための大きなモチベーションとなる。そういった意味で、僕たちのアニキにはとんがっていて欲しいと思うのは僕だけではないはずだ。
「15年前のULに反応した人たちっていうのは、ダサいからかっこよかったっていうのかな。スタイリッシュじゃない、イナたいかっこよさ。そういうのが、たぶんULの雰囲気の全体にあったんだと思う。それをもう一度ってわけじゃないんだけどね。」

00年代、日本のUL黎明期の土屋さん(写真提供:土屋智哉)
いまは、ハイキングじゃない
今回のHLCのツアーで行く先々で、僕は出会った人たちに同じ質問をした。「明日の朝、少し山に行きたいんだけど、さっと登って帰ってこれるところってない?」と。
200メートルの里山から、1000メートルのちょっとした山までみんな色々と教えてくれ、僕は、翌朝アドバイスに従って山に向かった。早朝の山には、毎日来ているようなおじいちゃんや、トレイルランナーや、犬を連れて散歩に来ているような人が必ずいた。それは、計画し準備していくようなイベントごとではない日常の山の風景だった。僕は、旅の間に身についた、毎朝近くの山に通う習慣がとても気持ちよくなった。出勤前のサーファーが、夜明けの海にワンラウンドだけ入るように、生活の中に山が無理なく溶け込んでいるような毎日を送ることが。僕は、裏山みたいなところでやれることの可能性の奥深さに気づいてしまったのだ。
「東京でやっているとローカル色ってなかなか出しにくいけど、街と山の間にあるのがいいなと思い、ここでやるこことにしたんです。中央線の沿線なので、山に行くのにも近いし。だから、うちの裏山は奥多摩や奥秩父。ULだと、裏山でも十分冒険になって楽しめるからね。」
地産地消という言葉があるが、自然やフィールドにも同じことが言えると思う。北海道には北海道のスタイルがあるし、九州には九州のオリジナリティーがある。それぞれの土地や風土や慣習に寄り添った流儀があって、それが面白い。そういう意味で、ハイカーズデポは、東京というローカルに根付いているんだと僕は思った。
「例えば、『うちはネットでも買えるけど、四国のメーカーだし、四国の人に使ってもらいたいから、四国の店にしか卸さないよ』ということが、これからはあってもいいんじゃないかって思う。『四国に良い山あるんで、ついでに四国にぜひ来てください』ってなると面白いなって。モノづくりとかモノ売りが、その流れにリンクしていければ、ローカル色ってもっと強くなるだろうし。そうやってコミュニティーができてくると、さらにライフやハイクにリンクしていくことはできるのかなって思いますよね。」
土屋さんのそのアイデアにはまったく同感だった。HLCで旅したいま思うのは、「日本全国どこも良い」ということだった。それぞれの土地にはそこだけの良さが必ずあった。
最後に、土屋さん自身の最近のハイキングについて聞くと、土屋さんはしばらく考えてこういった。
「今は、ハイキングじゃないんですよ。」
意外な返事に僕は驚いた。
「僕は今、西表島がいちばん面白いんですよね。もう何年もアウトドアの仲間と訪ねては探査してるんだけど、どっちかっていうと、自分の中では探検やってた大学時代に帰ってる感じなんです。自分が野外活動が好きになった初期衝動を、もう1回味わいに行ってる。学生時代の活動が、僕にとっての貯金になってたんです。もちろんハイキングもそうなんだけど、自分の初期衝動って何だろうって思ったら、やっぱりそこなんですよね。だから、今、あらためて栄養補給をしている。そうすることで、逆にハイキングの良さも見えてくる。」

西表島(写真提供:土屋智哉)
土屋さんは、西表で過ごす時間をハイキングじゃないと説明したが、それもまたハイキングと呼んでもいいんじゃないかと僕は思った。自分自身の源泉へと向かうハイキングだと。僕はハイキングを概念化しすぎているだろうか。むしろ、それはハイキングの先に続く「ライフ」に向き合っているというべきなのかもしれないと、僕は考え直した。
「昔の集落があったところや旧道も調べたいなって思ってる。人の痕跡とかも含めて見てみたい。歩いて回る地域研究に近いですよね。絶景を見るために山を歩いているわけじゃなくて、本当にそこにいるだけで満足という感じが出てきて面白いんですよ。」
ハイカーズデポと土屋さんは、大きな意味での次の展開に入ってきてるようだった。それは同時に、日本のULハイキングの新しい物語が始まったということかもしれない。僕は、土屋さんとハイカーズデポ、そして、みんなのハイキングが今後どうなっていくのかが楽しみになった。僕も、その世界の端っこで一緒に歩きながらその風景を見ていたい思った。
良いハイキングは、良いライフがあって成り立つものだと思うし、逆に、良いハイキングが良いライフつくる。どちらも完全に切り離されたものではなくて連動していている。「ハイキングが非日常のできごとではなく、日常の中ですべてとつながっている」という、このツアーを始めるときには仮説だった考えが、土屋さんの話を聞きながら、僕の中で確信に変わっていった。
【#24に続く】
『ゼロ年代からのハイキングコミュニティ』土屋智哉

1971年生まれ、埼玉県出身。東京・三鷹にあるルトラライト・ハイキングをテーマにした専門店「Hiker’s Depot」(ハイカーズデポ)のオーナー。古書店で手にした『バックパッキング入門』(山と渓谷社)に魅了され、大学探検部で山を始める。のちに洞窟探検に没頭する。アウトドアショップのバイヤー時代にアメリカでウルトラライト・ハイキングに出合う。このムーブメントに傾倒し、自らの原点である「山歩き」のすばらしさを再発見。2008年、ジョン・ミューア・トレイルをスルーハイクした後、幼少期を過ごした三鷹で同店をオープン。現在、ショップ経営の傍ら、雑誌やウェブなど様々なメディアで、ハイキングの楽しみ方やカルチャーを発信中。著書に『ウルトラライトハイキング』(山と渓谷社)がある。