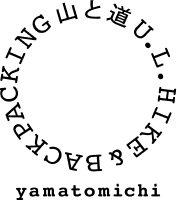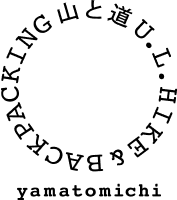アメリカ東部のアパラチアン山脈沿いに3500kmに渡って伸びるアパラチアン・トレイル(AT)は、「トリプルクラウン」と呼ばれるアメリカ3大ロングトレイルのひとつにして、もっとも長い歴史を持つ始祖でもあります。
2019年、イラストレーターにしてロングディスタンスハイカーの”Sketch”こと河戸良佑さんが、彼にとって「トリプルクラウン」最後の1本となるATに挑みました。この連載では、5ヵ月に及んだその長大な旅の模様を綴っていきます。
ともあれ、彼が以前同じく「トリプルクラウン」に挑んだ連載『コンチネンタルディバイドトレイル放浪記』を読んでくれた方ならご存知の通り、今回も「トリプル・クラウンを制覇するんだ!」的な気負いはゼロ。よく言えば自然体、というかノープランなSketchワールド全開で、彼の覗いたアメリカのロングトレイルのリアルを活写していきます。
さて、第2回目となる今回でも、前回と同じニールズ・ギャップの安宿のベッドにいるSketch。彼の頭の中に、そこに至るまでの様々な出来事が去来します。

Appalachian Trail
アメリカ東部のアパラチアン山脈に沿ってジョージア州からメイン州まで14州をまたいで伸びる約3,500kmの超ロングトレイル。開拓時代の旧跡も多く巡るルートはアメリカのルーツに触れる旅としての側面もあり、毎年数千人が踏破を試みる。
スルーハイキングの費用
アパラチアン・トレイルの始点であるストリンガー・マウンテンから、それほど離れていないニールズ・ギャップの安宿の一室で僕はベッドで横になり、ぼんやりと汚れた天井を眺めていた。
無機質なコンクリート壁の薄暗い部屋に8台の二段ベッドが押し込まれている。いわゆる「バンクルーム」と呼ばれるものだ。日本の宿泊環境と比較するとかなりひどく思えるかもしれないが、ハイカーにとっては屋根とシャワーとコンセントさえあれば、まるでリゾート地のホテルにいるような気持ちになる。

雨で濡れたウェアを2段ベッドに無造作にかけて乾かす。
ふと、あることが脳裏をよぎり心をざわつかせる。ひとつは資金のこと、ひとつは女性のことだ。落ち着かせるために僕はそっと目を瞑る。
アメリカでのスルーハイキング中は主にテント泊で自炊をして過ごすので、かかる費用は一般的な海外旅行よりも格段に安い。それでも6ヶ月弱を過ごすのだから、それなりにまとまった金額が必要だ。
海外から訪れるハイカーだけでなく、実はアメリカ人のハイカーですら、この予算について頭を悩ませている。なぜなら、多くのスルーハイカーは職が無く、その後の生活のためにできるだけ予算を抑えギリギリのラインを算出しようとするからだ。
この予算に関しては僕は過去にパシフィック・クレスト・トレイル(PCT)とコンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)をスルーハイキングした経験から、個人的な基準を既に見出していた。

雨が降らなかったらテントすらいらない。こんな状態だと逆にお金を使う方が難しい。2017年のCDTにて。

2017年のCDT終盤のニューメキシコ。この辺りで僕のハイキングスタイルはほぼ確立された。
スルーハイキングの場合、おおよそ4-7日の無補給ハイキングを6ヶ月弱の間、連続して行うことになる。そこで僕はまず1週間の費用を算出して、それから自分が何週間で踏破できるかを考えるようにしていた。
スルーハイキングは雪解けの春に出発し、雪が降り始はじめる晩秋には歩ききるのが基本になっているが、今回のアパラチアン・トレイルは低山のため積雪の心配があまりない。だからビザの期限の上限6ヶ月はトレイル上でのんびりと過ごし、できるだけ遊び尽くそうと決めていた。
余裕を持って帰ることを考えると、スルーハイキングに要する期間は22週ほどが妥当だろう。1週間の予算は25,000円というのが僕の基準だ。
ベッドの上で寝返りをうち、内訳を頭の中で再計算する。
僕のハイキング時の食事は、朝にスナック菓子、昼はサンドウィッチ、夜にパスタかライスを調理する。ほぼ毎日この繰り返しで問題はない。

トレイルでのいつもの食料。単調な食事だが、僕はあまり飽きを感じない。街に降りて補給する際も必要な分量が分かりやすく、無駄に時間を費やさなくて良い。

5日ぶんの食料を積むとこれくらいのザックの大きさになる。7日ぶんになるとかなり重量が嵩み、僕はかなり疲労を感じてしまう。
朝のスナックはチョコバーが3本と考えて500円。昼のサンドウィッチはベーグルにチーズと肉を挟むだけなので500円。パスタかライスは安価なクノール製品を買って200円。これに加えて行動食は、もっぱら朝食と同様のチョコバーを食べて続けるので1日に6本ほどで1,000円。つまり1日の食費は合計2,200円。7日で15,400円。あとの10,000円は、トレイルを歩かない休息日=ゼロデイに安宿に泊まってビールを飲む費用にあてる。
1ヶ月で10万円、6ヶ月だと60万円あれば、アパラチアン・トレイルを全行程歩くことができる。実際は5ヶ月程で踏破できるであろうから、浮いたお金はハイキング用品の買い足しなどに当てることができるだろう。
だが、困ったことに出発のひと月前の時点で僕の予算はこの60万円に全く達していなかった。そのことを思い返すと今更ながら自分で自分に呆れてしまう。

安いモーテルのシングルルームをシェアすることもある。モーテルの無料モーニングは貧乏なスルーハイカー達の格好の餌食だ。
ちょうど1ヶ月前のことだ。僕は銀行の預金残高を見て言葉を失った。なんとそこに8万円しかなかったのだ。すでに航空券分は引き落とされていたので、アメリカに行くことはできるが、この予算では当然ながらスルーハイキングは不可能だ。
「あと52万円……」僕は頭を抱えた。まだ未払いの原稿料がいくらか入ってくるはずだが、それでも全く足りない。すぐに「何か仕事をください」と懇願の電話とメールを方々に乱射することにした。
有難いことに十分な量のイラストとライティングの依頼を獲得することには成功した。僕の切羽詰まった状態に同情して、関係者方々が仕事を作ってくれたのだろう。しかし、今度はそれらを消化することに追われて、出国の当日を迎えてもなお仕事を終えることができず、もちろんのことながらハイキングの用意も全くできていない地獄のような状態での出発になってしまった。

足りない道具は現物を頼み込んで頂いたりもした。アウトドアギアマニアックスのスティーブ・マイヤーズさんとローローマウンテンワークスの谷口亮太郎さん。

自宅を出発する3時間前の写真。ここまできたら僕はもう諦めに近い心持ちになっていた。
とにかく必要であろう道具をバックパックに詰め込んで日本を飛び出した僕は、格安航空券のお約束、長時間のトランジットのため、ロサンゼルスで12時間足止めを食らった。ただ、僕はこの時間を利用して2015年にPCTで出会った女性と会う予定があった。
ネイキッド・ハイカーのダンディー

ダンディーとベニスビーチを歩く。
「やあ! スケッチ!」
ロサンゼルス国際空港のピックアップエリアに寝不足で呆けたように突っ立っていると、3月の西海岸の日差しを反射したような明るい女性の声が背後からした。振り返らずとも誰だか分かる。2015年にPCTを共にハイキングしたダンディーだ。日本を出国する直前に、彼女は僕に「LAに来るって聞いたわ。時間があったら案内してあげる」と短いメールを寄こしてくれていたのだった。
4年ぶりの再会だが、目の前にいる彼女は昔のままだ。PCTのワシントン州のトレイル上で話して以来だろうか。波のようにうねるブラウンの髪をなびかせ、満面の笑みで立っている。あまりにも変わっていないので、僕は時間がそのまま巻き戻されたような奇妙な感覚にとらわれた。

ワシントン州のホワイトパスでダンディーたちと過ごした写真。
長いハグをした後にありきたりなお互いの近況を話し終えると、彼女のクルマに乗り込んだ。
「僕は10時間後までにここに戻ってこれたらいいんだ。だから、それまで何もすることがない。今から何をするか決めてる?」
「今日は1日休みだから、どこでもいいわよ。とりあえず散歩でもしましょうよ。」
ダンディーはそう言うとゆっくりとクルマを発信させる。
「ねえ、今は何の仕事してるの?」
僕は殺人的な交通量のハイウェイを眺めながらたずねる。
「LAでウェイトレスよ。結構いい稼ぎになるの。でも、そろそろどこかへ移動しようと思っているわ。」
「どこかって?」
「インドかしらね。なんだかそんな気分なの……」
ダンディーはそう言うと、前方をジッと睨みつけた。
「どうしたの?」
「わたし、LAに来るまで運転したことなかったのよ。だから、この都市のクルマの量には本当に参ってしまうわ。」
世界屈指の交通量を誇るLAのハイウェイ。その上を川の流れに飲まれた木の葉のようにふらふらと運転する彼女を見て、早く3輪タクシーのリキシャが走るインドに行くべきだっと思った。

都心から離れてやっと車内で会話する余裕が生まれた。
僕がダンディーと初めて出会ったのは2015年にPCT序盤の小さなリゾートタウン、アイディルワイルドだった。資金が乏しい僕は高級なロッジに泊まることができず、町外れにあるキャンプサイトを目指して歩いている道中、買い出し終わりの彼女とすれ違った。
スルーハイカー同士はお互いをすぐに察知することができる。移動し続ける「ハイカートラッシュ」達たちは文字通りゴミ(=トラッシュ)のように小汚く、どの街にいても異質で浮いた存在だからだ。
「この近くにキャンプサイトがあると聞いたのだけど、どこにあるか知ってる? さっきから探してるけど見つからないんだ。」
彼女は立ち止まり僕に優しい笑みを投げかける。
「入り口が分かりにくいのよ。私もそこに泊まっているの。すぐ近くだから案内してあげるわ。」
彼女は良く言えば気さくな、悪く言えば少しドジな性格だった。背の低い彼女は僕と話す時にずっとこちらを見上げる。それでいて話が長いので路面を見ることを怠り、何度もつまづき、いちどは大きく転倒し側溝にはまった。それでも明るく笑う彼女はとても素敵で、僕は一瞬で好きになってしまった。
「ねえ、ダンディー。 もしよかったらこの後ディナーでもいかないかい?」
PCTで初めて女性を食事に誘ってみた。
「スケッチ、ごめんなさい! 実は私、今からトレイルに戻るのよ。」
早くも敗北を期した僕であったが、これから5ヶ月以上も同じトレイルを歩くのだから、何度でもチャンスはあるはずだ。別段気にせずに彼女を笑顔で見送った。

ダンディーが去った後はむさ苦しい面子しか残っていなかった。
しかし、再会することがなく1ヶ月が経ち、彼女のことを忘れかけていた頃、カリフォルニア・セクション中盤の砂漠の真ん中で衝撃的な再会をした。
本来ならば飛び上がって喜ぶところであるが、逆に地底に沈み込んでしまいたい気持ちになったのは、テントを建てずに地面の上でそのまま眠るカウボーイキャンプしていた彼女の寝袋に、男性が一緒に収まっていたからだ。
全てを悟った僕は、砂漠のトレイルに乾燥した小さな足音だけ残して立ち去るしかなかった。
その後、ダンディーのパートナーはポンチョというハイカーだと、ハイカー仲間の情報からすぐに判明した。彼とはこれまで何度か話したことがあり、とても気持ちの良い男性だった。どこかアメリカ人らしからぬ大味でない性格が彼女とお似合いに思えたので、僕は多少の傷心を負いながらも、ふたりを微笑ましく眺めていた。

砂漠には何もない。僕の心の中も乾いて空っぽになる。
さらに衝撃的な事件が起きたのは、3週間後のPCTカリフォルニア・セクションの終盤、かの有名なジョン・ミューア・トレイルでのことだった。
その日、ふたつ目の大きな峠を登り終えた僕は、見晴らしの良い場所で休憩しながらコーヒー用の湯を沸かした。風が強いので岩陰に身を寄せて、顔だけ出して景色を眺めていた。切り立った岩壁に引っかいたような細いトレイルがスイッチバックを繰り返して伸びている先に、小さな影が動いているのが見えた。ハイカーがこちらに向かっている。南下ルートが主流のジョン・ミューア・トレイルを北上しているということはPCTハイカーであろう。

JMTは峠から見下ろす景色がとても美しい。僕は遠くで小さく動くハイカーの影をのんびりと眺めるのが好きだ。
影は次第に大きくなり、ハイカーの姿が明瞭になってきた。その顔に見覚えがある。目を細めてじっと見ていると、それがポンチョだと分かった。しかし、どこか奇妙である。徐々に彼が近づくにつれて理由が分かり、僕は絶句した。
高度3000メートルの澄んだ冷たい空気と西海岸の強い日差しに晒された彼は、なんと全裸だったのだ。
3ヶ月強ハイキングし続けた彼の歩みには一切の迷いはを感じさせない。彼はリズミカルに左右の足を動かし、それに呼応して彼の股間のハイキング・バディもメトロノームの如く小気味良く揺れている。
これは噂に聞くネイキッド・ハイカーだ! 僕は岩陰に身を潜め異様な光景を眺める。よく見るとしっかりとソックスとシューズは履いている。やはり、そこは必要不可欠なのか、と僕はハイキングの深淵を覗いた気がした。

6月のJMTにはまだ氷が張っている箇所がいくつかあった。
ふとダンディーのことを思い出す。申し訳ないがポンチョはもう頭がおかしくなっている。そんな彼と付き合い続けるほど、彼女は変人ではないはずだ。つまり、諦めていたチャンスが全裸男と共に到来したのだ。
とっくに沸いていた湯にインスタントコーヒーの粉末を溶かして飲む。脳裏にチラつくポンチョのイチモツと舌に広がるコーヒーの苦味。僕の心は晴れやかだった。
ポンチョとの距離はどんどん広がり、とうとう見えなくなる。岩陰から出て、コーヒーを飲みながら先ほどと同じように山脈を眺めた。
すると、またひとり、ハイカーが歩いてくるのが見えた。まるで先ほどのデジャヴのようだ。同時に確信に近い不安が僕を襲い始めた。
まるで悪夢の答合わせをしているように、まずそのハイカーがダンディーだとすぐに分かった。そして、彼女は当然の如く全裸だった。

余談だが、僕はJMT区間で完全に食料が尽きてしまい。すれ違うハイカーに食料を恵んでもらって生きていた。一度だけ野草も食べた。
僕はパニックになった。今まで生きてきて、好意を寄せる女性がトレイル上で裸でこちらに向かってくるという経験は初めてだ。一応、靴下とバックパックとトレッキングポールは備えている。
僕はどうしたら良いか分からず、無意識のうちに岩陰で身を丸めて隠れていた。彼女の足音がかすかに聞こえる。先ほどまでの期待は何処へやら、今はただただ混乱の渦に身を任せるのみである
岩陰で身を丸めて少し経ってから、ふと「もうこうなったら、彼女の裸を拝むべきなのではないだろうか。いや、逆に見ないというのは不自然な行為である!」という思いがふつふつと沸き起こってきた。ここはアメリカ、自由の国だ。
意を決して飛び出す。という訳にもいかず、彼女が過ぎ去ったことを確信してから、こっそりと岩陰から這い出た。
少し離れたところに裸のダンディーはいた。しかし、小柄な彼女をベアキャニスターを収納して大きく膨れ上がったバックパックが覆っていたため、僕が見えたのはそこからスラリと伸びる綺麗な2本の脚だけだった。

JMTでハイカー達と泥の温泉に浸かる。全裸のハイカーはひとりもいなかった。
スルーハイキングを通じてトレイルを共有したハイカーと再会するときは、いつも奇妙な感じがする。
お互い住む国が違って、長らく会うことがなくても、結局は我々は同じ種類の人間で、似たような領域で活動し続け、そこから出ることができない。だから、再会も偶然ではなく、長らく会っていなかった同級生に最寄りの駅で出くわすようなものなのだ。実際に再会してクルマを運転する彼女の横顔を見ていると、やはり奇妙な感じがする。

トレイルを歩くダンディーは以前と変わらず軽やかだった。
僕らは海岸線をドライブしてLAから少し離れた小さな丘を登ることにした。海岸沿いの小さな駐車場からほんの20分ほど歩くと、大きな岩が並ぶ丘の上に辿り着いた。
岩の上に座り、ダンディーが持ってきたタッパーに入ったカットフルーツを食べる。日差しは強いが、空気が乾燥していて風が冷たいので気持ちが良い。眼下に広がる太平洋ではサーファーたちがゆらりと浮んで波を待っている。
とくに会話もせずにふたりでじっと景色を眺める。そして30分ほどすると僕らはその場を後にした。スルーハイカーはひとつの場所で長い時間を過ごすことができない。それは、次に訪れる景色が待ち遠しいからではないか、と僕は考えている。
彼女に会うまでは、何か心躍る感覚があったのだが、今はもうない。おそらく、僕の気持ちは完全にアパラチアン・トレイルに向かっていて、彼女は気持ちはアメリカではないどこか遠くの土地に向かっていたからだろう。
その時、僕は彼女と会うのはこれが最後ではないだろうか、と思った。

遠くを見つめるダンディー。見つめる先はインドなのだろうか。
マタドールとの再会
コンベアを流れるバックパックを回収し、空港の外に出ると、東海岸の湿気を含んだ暖かい空気が僕を迎えた。まるで日本の夏のような気候だ。ダンディーと別れた僕はふたたび飛行機に乗り、東海岸のジョージア州ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港に到着した。
日陰に移動し、友人のマタドールが迎えにくるのを待つ。マタドールもまた2015年にPCTで苦楽を共にした仲だった。彼はアメリカ国内をハイキングやトレイルランニングをしながら車上生活していたが、この4月からアパラチアン・トレイルでレンジャーの職に就くことが決まり、故郷のアトランタに戻ってきていたのだ。

スケッチ(左)、マタドール(中央)、マーマン(右)。僕らは2015年10月3日にPCTを一緒に歩き終えた。
スマートフォンが振動する。マタドールからの着信だった。
「やあ。今、空港の外で待ってる。」
「分かってるさ! 俺は君の目の前にいるぜ!」
顔を上げると、そこには白いバンがゆっくりと徐行していて、運転席を見るとマタドールがこちらを見てニンマリと笑っている。
「ここじゃ停車できない! 飛び乗れ!」
彼が叫んだ。僕は急いでバックパックを担ぎ走り出す。まったくそれだったら停車してから電話して欲しいものだ。
徐行するクルマに追いつき、助手席のドアを開けると、まずバックパックを投げ入れ、そして僕の体を滑り込ませる。アメリカではこんなドタバタ乗車劇が茶飯事なのか。

マタドールに連れられてオススメのスムージーを購入する。彼の左腕には歴史が刻まれている。

クルマを売りたいマタドール。フロントガラスに”For Sale”と書かれた紙を貼ったまま走行していた。
「ヘイ! スケッチ! ようこそアトランタへ! 調子はどうだい兄弟?」
「どういうわけか、ちょっとした運動をしたから、気分は悪くないさ。」
「本当に久しぶりだな! 何も変わってないな!」
マタドールは綺麗な青い瞳を細くして笑った。
「君はタトゥーが増えたね。」
「ははは。そうなのさ。」
彼はそう言って左腕を上げた。
「これがPCTのタトゥー、ワシントン州で森が黄金に紅葉していただろ。あのとき森だ。これはCDTをハイクしたときの、そしてこっちがアリゾナ・トレイルでFKT(最速記録)を更新したときのもので……」
マタドールは運転しながら左腕に新しく彫ったタトゥーの説明する。彼はすでにAT、PCT、CDTを踏破してトリプルクラウナーになっていた。アリゾナ・トレイルに関しては3回もハイキングし、3度目に2019年時点でセルフサポートの最速記録を打ち立てていた。
アトランタのダウンタウンをクルマは走る。アトランタは僕が今まで訪れた都市の中でいちばん黒人の比率が多い。至る所にグラフィティがペイントされていて、道ゆく人はどこか陽気に感じる。治安が悪いとされているこのエリアだが、刺激的な雰囲気が僕の心を躍らせていた。
「ところで、今からどこに行くのだい? だって君は家がないだろ?」
「今から俺の親友の家さ。広いからふたりなんて余裕で泊まることができる。」
ハイカー仲間と再会して、とても心が落ち着くひとつの理由として、物の価値観、つまりは金銭感覚ということになるのだろうが、これが共通しているというのがある。
僕らは多くは裕福ではなく金銭に無頓着だ。そもそも消費することに対して然程幸せを感じない。必要なのは温かいシャワーと冷たいビール、そして、贅沢を言えば清潔なベッド。それだけで十分なのだ。

マタドール友人とその彼女。近くのスーパーのフードコートで食事をする。ふたりとも笑顔が絶えず気さくなので、すぐに仲良くなった。
「スケッチ、もうすぐ出発なのに大丈夫か?」
マタドールの声で目が覚めた。喉が乾き切っていて痛い。彼が運んで着てくれたグラスに入った水をゆっくりと飲む。
「たぶん大丈夫じゃない。」
荷物が散乱していた部屋の真ん中で寝ていた僕は体を起こす。昨晩、マタドールと友人のフレッドと飲みすぎたせいで頭が重い。

アパラチアン・トレイルへ向かう当日朝の様子。前日に深酒をした為、何も用意できずにいた。
「これ全部運ぶつもりじゃないだろ?」
「さすがに荷物が多すぎるから、あとで郵便局に連れて行ってもらってもいいかい? 友人の家にいくらか送りたいんだ。」
日本を出る際にまともに考慮せずにパッキングしたため、不必要なハイキング用品まで持ってきてしまっていた。僕はテント、寝袋、クッカー……重要度が高いものを順にバックパックに放り込む。そして、余ったものはダンボールにまとめてクルマに積む。
この日、僕らは同じくアパラチアン・トレイルを歩く予定のマタドールの友人、トロイを空港まで迎えに行かねばならなかった。
トロイは色白の金髪長身で190センチほどあって、手足がとても長い。マタドールから彼はロング・ディスタンス・トレイルは今回が初めてと聞いていたが、痩せ型で下半身の筋肉が逞しい体型から屈強のハイカーたちと似た雰囲気がした。

アパラチアン・トレイル前のランニングセッション。もちろん僕は参加せずに公園のベンチで昼寝をしていた
「ねぇ、トロイ。君は何かスポーツとかしていたの?」
「俺はトレイル・ランナーさ。でも、こんなに大きなバックパックを背負って歩くのは初めてだから、かなり心配なんだ。」
彼のバックパックははち切れんばかりにパンパンで、明らかに不必要なものがたくさんパッキングされているようだ。
クネクネと山の中に伸びるハイウェイを3時間ほど走りアミカローラ・フォールズ州立公園のビジターセンターに辿り着いた。
ほとんどのハイカーはこの地点から8.8マイル歩いて、アパラチアン・トレイルの南側のスタート地であるストリンガー・マウンテンへ向かう。ストリンガー・マウンテンの近くのまでクルマで行っても問題はないが、このビジターセンターにはアパラチアン・トレイルのスタートの象徴である石造りのゲートがあり、そしてATハイカーの登録をするとプレートと番号をもらえる。ハイカーたちはバックパックにプレートを付けて自らがATハイカーであることを示し、書かれた番号で自分が今期何人目のハイカーなのかを知ることができる。

ビジターセンターへ向かう一同。
ビジターセンターに到着すると別室へ案内される。石造りの綺麗な建物の一室には15名ほどのハイカーが既に待機していた。おそらく一日何回も行われているのだろう。そう考えると、ものすごい数のハイカーがここに訪れることになる。
2年前のCDTは南下するハイカーが50人にも満たなかったことからすると驚くべき違いだ。テーブルの上にあるレジスターに名前を記入する。その横に「2135」と記されていた。なるほど、僕は2019年アパラチアン・トレイルを2135人目にスタートするハイカーだ。
その後、レンジャーからハイキングに関する簡単なレクチャーを受け、それが終わるとハイカーたちは石造りのゲートで記念撮影をして出発しはじめた。僕らも3人で写真を撮り終えると、トロイはあっさりとその場を去っていってしまった。

3人で記念撮影。トロイはこの後すぐに出発していった。
僕は急ぐ気もないので、ベンチに座ってハイカー達がスタートしていく様子を眺めながら「この中の何人が最後まで歩き切るのだろうか」と考えた。
アパラチアン・トレイルの踏破率は20%といわれている。これには諸説あり、ゴールを申告しないハイカーがいたりすることから、実はもっと高いのではないかとも言われているが、僕は20%という数字は妥当であると考えていた。
そう考えると、一緒にレクチャーを受けたハイカーのうち3人しか、最終目的のメーン州カタディンに辿り着けないことになる。
初日でふたりのリタイア

簡単なスケッチ。水彩絵の具を使用したことがほとんどないので、いまいち要領が分からない。
簡単なスケッチを終えると、いよいよ3メートルほどの高さの石造りのゲートをくぐった。そこから伸びるトレイルはなだらかで地面がきちんと整備されていて歩きやすい。
20分ほど歩くと木製の階段が現れた。その先ではジョージア州で最も高い222メートルのアミカローラ滝が水しぶきを立ててハイカーたちを迎えている。ここからは木製の階段をひたすら上まで登らなければならない。登り始めは滝から舞う霧で涼しかったが、それでも湿度の高い東海岸の気候はすぐに僕の体を汗でぐっしょりと湿らせて不快な思いにさせる。

アミカローラ滝を登る木製の階段。
黙々と登り、疲れると滝を見ながら休憩をする。階段の中間地点にたどり着くと、そこは踊り場になっていて、20代の若い女性ハイカーが手すりを持って立っていた。彼女も一緒に先ほどのレクチャーを受けていたATハイカーだ。
「やあ! 調子はどうだい?」
すると、彼女は表情を歪ませた。
「どうやら、良くないようだわ。」
「どうしたの?」
「すごくしんどいのよ。」
「どこか具合でも悪いのかい? 何か助けがいるかい?」
僕は心配になり、彼女に近づく。どうやら、本当に苦しそうだ。
「いえ、違うのよ。ハイキングがこんなにしんどいなんて、私、知らなかったわ。」
「え? なんだって……」
僕の聞き間違いだろうか。まだ序盤の階段を半分登っただけである。
「もう無理。私、帰る。」
彼女はゆっくり階段を降り始めた。僕は呆気にとられて彼女の後ろ姿を見つめる。一体何が目の前で起こっているのだ。

実際のところ年配の方が登ることができるほど簡単な階段だった。
滝を登り終え、小さなアップダウンを繰り返すトレイルを黙々と3時間歩くと、やっとアパラチアン・トレイルのスタート地点であるストリンガーマウンテン山頂に到着した。
山頂には岩に埋め込まれたプレートがポツリとあるだけ。そこで初めてジョージア週の山の景色を眺めることができたが、ただ低く延々と森が続くのみだった。
今日は遅くまで歩くつもりはなく、2時間ほど歩いた先にあるシェルターに行ってみることにした。山頂からのトレイルは落ち葉が敷き詰められていて、ふかふかと気持ちが良い。思わず歩みを速める。
休憩することなく一気にシェルターにたどり着いた。人生初体験のシェルターであるストーバークリーク・シェルターは内部が2階建てになって、とても清潔で綺麗だ。この様なシェルターがトレイルに点在しているなら、テントなんて持ち運ぶ必要はないのかもしれない。

木造の綺麗なストーパークリーク・シェルター。
シェルターには先客が男性と女性がいた。どちらもビジターセンターで見た顔だ。僕は男性の方にまず近寄り挨拶をする。どこかキザな雰囲気の中肉中背の40代男性だ。そして、シェルターから少し離れたところに立っている30代の女性の方へ行って話しかける。
僕は彼女の顔を見て驚いた。泣いていたからだ。
「大丈夫かい? どうしたの?」
彼女は僕に気がつくと、強がって笑顔を作った。
「モバイルバッテリーがないのよ。」
モバイルバッテリーが無いとスマートフォンを充電できない。彼女がオンラインマップのみ使用していたのならば心配だ。
「それは困った! とりあえず、今夜は僕のバッテリーを使いなよ。ハイカーはみんな持ってるし、新しいのを買うまでは人から借りたら問題ないよ。」
「もういいのよ。」
「どういうことだい?」
「私さっき、ママに電話したの、そしたら明日の朝に近くの駐車場に来てくれるって。」
30分ほど歩いた先に駐車場があったはずだ。いきなり母親をこんな山奥に呼びつけるのはいささか乱暴ではないか、と思ったが口にはしない。
「よかった! 明日、バッテリーを受け取れるんだね!」
「あなたなに言ってるの? 違うわよ。私は明日、母と家に帰るのよ。バッテリーなんてもういらないわ。」
なんと初日にしてふたり目のリタイアだ。僕は激しく混乱した。皆、それなりの覚悟でアパラチアン・トレイルに挑んでるのではないのか。階段とモバイルバッテリーでスルーハイキングを諦めるなんて間違っている。その日の夜はシェルターで彼女と過ごす気分にもなれず、離れた場所にそっとテントを設営することにした。

ニールズギャップの宿のリビングの様子。
あれからニールズ・ギャップの二段ベッドで寝転がっている現在まで、親しくなれたハイカーはひとりもいない。もしかして、とてもつまらない自らハイキングをしているのではないか。僕にとってダンディーやマタドールのような出会いがトレイル上では何よりも刺激的で、素晴らしいものだったはずだ。
僕は急に不安になり、二段ベットから飛び降りて焦る気持ちでリビングへ向かった。
【#3に続く】