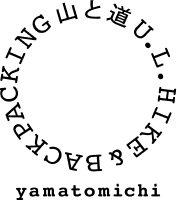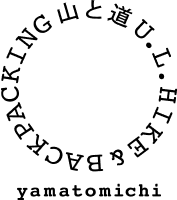アメリカ東部のアパラチアン山脈沿いに3500kmに渡って伸びるアパラチアン・トレイル(AT)は、「トリプルクラウン」と呼ばれるアメリカ3大ロングトレイルのひとつにして最も長い歴史を持ち、また最も多くの人が歩く、まさに「ロングトレイルの中のロングトレイル」とも呼べる存在です。
2019年、イラストレーターにしてロングディスタンスハイカーのトレイルネーム”Sketch”こと河戸良佑さんが、彼にとって「トリプルクラウン」最後の1本となるATに挑みました。この連載では、5ヵ月に及んだその長大な旅を通じて、彼の覗いたアメリカのロングトレイルのリアルを活写していきます。
マサチューセッツ州に到達し、ついに旅も後半に差し掛かってきたSketch。長く続くトレイルでの生活にややマンネリも感じてきた彼に、ある印象的な出会いが訪れます。
今回もまさにSketchしか書けないリアルなアメリカのロングトレイルのスケッチに、ぜひお付き合いください!

Appalachian Trail
アメリカ東部のアパラチアン山脈に沿ってジョージア州からメイン州まで14州をまたいで伸びる約3,500kmの超ロングトレイル。開拓時代の旧跡も多く巡るルートはアメリカのルーツに触れる旅としての側面もあり、毎年数千人が踏破を試みる。
僕はマルティン
ロング・ディスタンス・トレイルをハイキングしていると必ず強く心に残る出会いがある。それはハイカーやトレイル・エンジェル、またヒッチハイクで偶然クルマを停めた人であったりする。
2019年7月26日、僕はマサチューセッツ州ダルトンから友人のクルマでアパラチアン・トレイルに戻ってきた。クルマの外に出ると東海岸の湿った空気が体にまとわり付き、じわりと染みた汗の臭いに誘われてたくさんの蚊が耳障りな羽音を鳴らしている。
「それじゃあ気をつけてな、スケッチ。」
運転席から友人のマーマンが言った。彼とは2015年にハイキングしたパシフィック・クレスト・トレイルで出会って、一緒にカナダ国境でゴールした仲だ。彼とその彼女は100kmほど離れたボストン郊外からわざわざ会いに来てくれていた。僕はふたりにダルトンでチャイニーズビュッフェをご馳走になり、その後に大型マーケットへ買い出しへ、さらにあらかじめ送っておいた荷物を受け取り、そして使わない装備を送るために郵便局へ行った。ハイカーにとって最高のガイドを受けて、最後はトレイルヘッドまで連れてきてもらった。

友人のマーマンのクルマはとてつもなく汚い。

ハイカーは食べ放題のビュッフェが大好きだ。マーマンももちろんそれを知っている。
しかし、今回の主人公はマーマンではない。彼らがその場で去ってから僕は駐車場所のすぐ近くからトレイルに戻ろうとしたが、すでに日が暮れ始めていたので、歩いて1時間ほど先にあるシェルターまで歩くのが次第に億劫になってきていた。それに駐車場の裏にはテントを10張りしてもまだ余裕がありそうなスペースがあった。少し地面は固いが、落ち葉が柔らかなクッションとなっていてとても寝心地が良さそうだ。僕はそのスペースの中の一等地を探し当てようとウロウロと彷徨っていた。
「ちょっと、いいかな?」
誰もいないと思っていた駐車場入り口の方から突然呼びかけられたので、僕は驚いて身構える。薄暗くて姿が見えにくいが、よく目を凝らしてみると大きなバックパックを背負ったハイカーが立っていた。
「やあ。調子はどうだい?」
僕が話しかけると彼は笑顔で歩み寄ってきた。身長は170cm程で、西洋人らしいガッチリとした体躯の青年だ。
「あのさ、君はATハイカーだよね?」
「ああ、そうさ。アパラチアン・トレイルをスルーハイク中だよ。」
彼の質問の意図がいまひとつ掴めずに、僕は少し素っ気なく答えてしまった。
「よかった! 迷惑じゃなかったら、君について行っていいかな?」
「申し訳ないけど、この辺でテントを張ろうと思ってるんだ。なんだか今日はもう歩きたくないんだよ。」
「じゃあ、同じようにここに泊まってもいいかな?」
青年は短髪頭をボリボリとかいて、少し困惑している表情をした。
「もちろん、いいさ。でも、2マイル先にシェルターがあるから、そっちまで歩いてもいいかもしれないよ。僕は面倒だからもうここで寝ちゃうけど。」
「2マイルか。」
「何か問題でも?」
「実はどっちに行けばいいのか分からないんだ。」
「どういう意味?」
彼がどのような意図で言ったのか分からなかった。ヨーロッパアクセントの彼の英語に慣れない僕が聞き取れなかったのかも知れない。
「実は地図がないんだよ。」
「地図がないのか。」
「そう、地図がないんだよ。」
僕は少し黙って「地図がない」という言葉の意味を考えてみたが、やはり「地図がない」とそのままの意味でしか理解できなかった。
「ごめん。君の言ってる事が理解できてないんだ。『地図がない』と言ったけど、それってそのままの意味で『地図を持ち運んでない』ってことなのかい?」
「そうなんだよ。」
「スマートフォンに地図アプリは入れてないのかい?」
「そんなものがあるのかい?」
「そんなものがあるのさ。つまり君は何のガイドも頼らずにトレイルを歩こうとしてるんだな。」
「その通りさ!」
彼は大きく口を開けて笑った。
「君はアパラチアン・トレイルを最初から歩いてきたわけではないのか?」
「実は、今日が1日目なんだよ。ボストン留学中の友達に遊びに来ていて、そのついでに2週間ほどアパラチアン・トレイルを歩いてみようかなと思ってさ。それで、少し前にここの駐車場に到着したのだけど、どっちに行けばいいか分からなくて困っていたら、君がクルマで来たのが見えたのさ。」
色々と不明点が多くて状況を把握することができずにいたが、彼がとても奇妙な奴だということだけは分かった。アパラチアン・トレイルは3大トレイルの中で最もハイカーが多い。だから、出会ったハイカーに道をたずね続けながら歩くことはできるだろう。しかし、そんな方法で歩こうとするハイカーを見たことも聞いたこともなかった。
「じゃあ、とりあえず今日はここで一緒にキャンプをしようか。そして、君はラッキーなことにここから3時間ほど歩いたところにチェルシーという街がある。そこで地図をダウンロードしたらいいさ。」
「ありがとう! ところで、僕はマルティン! 君は?」
「僕はスケッチさ。スケッチはトレイルネームだけどね。」
「よろしくスケッチ! 僕はトレイルネームはないのだよ。」
当たり前だ。彼はまだハイキングを始めてすらいないのだ。話を聞くと彼はスペイン在住の学生で、夏休みを利用してボストン観光のためにアメリカにやって来たらしい。

びっくりするほど長い紐でハンモックを張るマルティン。
話しているとすっかり日が暮れてしまったので、僕らはやっと寝床を設営することにした。僕はいつもと同じようにゴッサマーギアの非自立式テントを張り、大量の蚊から逃げるために素早くテントの中に潜り込んだ。そしてメッシュ部からマルティンを観察する。彼は木々の間を右往左往しながら、どうやらハンモックを設営しようとしている。おそらく本日初めて使用するのだろう。あまりにも長いロープに悪戦苦闘していた。30分ほどかけてやっとハンモックを張り終えると、彼は僕のテントの横までやってきた。
「どうしたの?」
「とくに用事はないのだけど、よかったら話でもしないか?」
僕にとってはいつもと同じ夜だが、彼にとっては今夜はアメリカのトレイルで過ごす最初の夜なのだ。これは僕の心配りが足りず申し訳なかったと反省した。僕はお詫びの気持ちを込めてココアを作りマルティンと話すことにした。この無謀な青年に徐々に興味を持ち始めている自分がいたが、それがなぜなのかよく分からなかった。僕らは互いに拙い英語で会話を続け、その間ずっと蚊に刺され続けていた。

僕のスケッチブックを見るマルティン。
翌朝、マルティンのうめき声で目が覚めた。テントの中は暗い。時計を見ると5時だ。まだ眠かったので寝袋に潜り込むが、時折聞こえる彼の呻うめき声を聴いているうちに観念してテントの外に出たると、彼はハンモックの側に立っていた。
「おはよう。よく寝れたかい?」
「全然寝れなかったよ。ひと晩中蚊に刺され続けたんだ。」
彼はそう言って弱々しく笑った。
「え? 君は蚊帳を持ってないのかい?」
アパラチアン・トレイルは虫が多いので、ハンモックを使用する場合は蚊帳を併用するのが一般的だ。
「いや、持ってない。」
「もしかして、タープも持っていないかい?」
「タープも持っていない。」
これには驚いた。雨の多いこの地域で彼は濡れることを全く想定していないのだ。そして彼は地図を持っていないため、僕と一緒でないと次の街へ移動すらできないことを思い出す。僕は急いでパッキングして薄暗い森の中を彼と一緒に歩き始めた。

木々が生い茂るアパラチアントレイル。
早朝のアパラチアン・トレイルが一番好きだった。日中は地獄のような蒸し暑さだが、この時間だけはひんやりと気温が低く気持ちが良い。
僕はアパラチアン・トレイルを歩くハイカーの中でも速い。それでもマルティンは遅れることなくついてきてた。装備はいい加減だが体力はとてもあるようだ。
いとしのマルティン
アパラチアン・トレイルは補給が容易なセクションが多い。特にこのマサチューセッツ州は街から街までの距離が近く、今回も休みなく3時間程歩くと目的地のチェルシーに到着した。このような近さだと立ち止まることなく通過するハイカーも多いのだが、僕らは朝からずっと朝食を食べずに歩き続けていたために空腹で、何よりもマルティンに地図アプリケーションをダウンロードさせる必要があった。そこで街のガソリンスタンドに併設されたダンキンドーナッツに開店時間と同時に入店した。
レジカウンターの立っているスタッフは気だるそうにしていて、小汚い僕らを見ると更に気だるそうに「なにかご注文は?」と尋ねた。
僕はボリュームがあるエッグベーコンマフィンとカロリーが高そうなチョコレートシェイクを頼んだ。
クレジットカードで会計を済ませたと同時に別スタッフが注文商品をトレイに乗せて僕へよこす。それを受け取ると窓際のテーブルに移動してマルティンを待った。
彼はホットコーヒーをすすりながらやってきた。
「朝ごはんは食べなくていいの?」
「あまりお腹が空いてないんだ。」
「そうなんだ。」
紙の包装を剥がしてマフィンにかぶりつく。ドロッとした脂が口の中に広がり、まずくて僕は顔をしかめる。そして、その味を忘れるように甘ったるいシェイクを口に含んだ。
「とりあえずさ。ガットフックという地図アプリをダウンロードしろよ。」
「それは無料?」
「いや、そこそこの値段だけど、必要だから仕方ないさ。」
マルティンはスペイン語で何かモゴモゴと文句を言って、スマートフォンをポケットから取り出したが何も反応がない。どうやら充電が切れてしまっているようだ。
次に彼はバックパックから小さな白い箱を取り出してきた。僕はそれが何なのか興味津々に観察していると、それはバックパッカーが持ち運ぶような電源プラグを変換する装置だった。テーブルの下のコンセントに変換プラグを差し、そこに細く丸い銀の筒が2本飛び出たプラグを組み合わせ、そして最後にUSBケーブルを接続した。しかしスマートフォンには全く充電が開始されない。それを見て呆然としているマルティンを見て僕は笑いを堪えることができなかった。
「一体どうなってるんだ!」
マルティンは叫んだ。あまりにも大きな声だったので、店員がこちらを訝しい目で見る。

充電がうまくいかず落ち込むマルティン。
「まあ、落ち着けよ。僕の充電器はふたつソケットがあるから一緒に充電しようぜ。」
僕は自分の充電器を取り出して、コンセントに挿そうとした時に手が止まった。彼の変換プラグにはすごく分かりやすい場所に、かつとても押したくなるような大きなスイッチがあったのだ。それを押すと、マルティンの驚きの声が頭上から降りてきた。
「スケッチ! 充電がはじまった!」
スペインの青年がいきなりアメリカの国立公園を繋ぐ旅に出たらどうなるのか? そんなドキュメンタリー番組を見ているようだ。
「ちょっと席を外すから荷物見てて!」
そう言うと彼は店の外に出て行った。いつも行動が急すぎて僕の状況把握が追いつかない。トイレにでも行ったのだろうか? いや、それなら外へ出る必要はない。窓越しに動向を見守っていると、彼はガソリンスタンドの脇に向かって行き、地面に置かれていた段ボールを拾い上げると、それを両手で大切そうに抱えて帰ってきた。
どうするのかシェイクをすすりながら眺める。彼は段ボールを手に取り大きなナイフで一片を裂いて広げたものを床に置いた。そうしてふたつ目に取り掛かろうとしたところで僕はたまらず質問した。
「一体何してるんだい?」
「マットを作ってるのさ。」
マルティンはこちらを見てにこりと笑う。僕は店内でナイフを出しているので通報でもされるのではなかろうかと少し恐怖していた。
「寝るためのマットかい?」
「そうさ。昨日の夜はどうも背中が寒くて寝れなくて。」
高温多湿のアパラチアン・トレイルだが、確かに夜は冷え込むときもある。しかし、昨日はそれほど寒かっただろうか? しかし、本人が言うならそうなのだろう。2枚の段ボールを床に並べ終えると、それらを今度はロール状に丸めて梱包用のロープで縛った。マルティンは満足した顔で席に戻り、コーヒーを飲み始めた。

戦利品の段ボールを嬉しそうに見せる。
僕らはハイキングと全く関係ない雑談をしてスマートフォンが充電されるのを待った。マルティンは隣街に住む彼女に会うために2時間自転車を漕いでるらしい。それであの健脚なのだろう。
地図アプリをダウンロードとスマートフォンの充電を終えると僕らはトレイルに戻るために店を後にした。すでに完全に日が昇り、いつもの蒸し暑さにうんざりした僕とは対象に、彼は嬉々としていた。それにつられて僕も幾分前向きな気持ちになってトレイルに戻った。
マルティンは底抜けに明るい性格の持ち主で、そしておしゃべりだった。ハイキング中はずっと話しかけ、そうでないときはひとりでスペイン語の歌を唄っていた。そして、やはり驚かされるのが体力だ。僕は試しにいつも通りの速度で歩いてみたが、彼は表情ひとつ変えずについてきた。
「なあ、マルティン。雨が降ったらどうするつもりなの?」
僕はずっと気になっていることを聞いてみた。
「え? 今から雨が降るのかい?」
「今からは降らないと思うけど、東海岸の森は雨がよく降るんだよ。」
1日のうちに通り雨に何度も遭遇してしまうのが、このトレイルの特徴でもある。
「雨が降らないように祈るのみさ。大丈夫な気がしている!」
「さあ、どうなんだか。」
確かに雨が降ったところで、この気温であれば全身がずぶ濡れになって不快な夜を過ごすくらいで、死んだりはしないから、そこまでは心配しなくてもいいのかもしれない。
僕らはチェルシーからマウント・グレイロックのエリアの中を伸びる登り坂をひたすら登っていた。2時間ほどで丘の上にある退役軍人の慰霊碑であるベテランズ・ウォー・メモリアル・タワーに到着した。
クレイジー・マルティン

ベテランズ・ウォー・メモリアル・タワーでフリスビーをするマルティン。元気いっぱいだ。
23メートルある白い石造のタワーは細長い円錐型でその上にガラスで装飾されたゆで卵のような球体が置かれていた。マルティンはタワーにあまり興味を示さなかったので、僕は建物にひんやりとした螺旋階段をひとりで登って外を見た。展望はとても良かったが、特筆すべきようなものは何も見当たらない。延々と続く退屈な森とその中に埋もれかかってる農場がポツポツと見えるだけだ。階段を登った分だけ損をした、そんな気分で僕はタワーを後にした。
外では長い木の棒を両手に携えたマルティンが満面の笑みで僕を待っていた。
「そんなものさっきまで持ってなかったじゃないか。」
「向こうにたくさん落ちてたんだ。スケッチ、君もいるかい?」
「残念だけど、僕はとても高価で軽量なカーボン製のポールがあるから遠慮しておくよ。」
おそらく、ここに来るデイハイカーたちが登るときに使用して捨てていくのだろう。
「見て! 見て!」
マルティンは片方の棒を前に突き出すように持ち、その上にもう片方の棒のを十字になるように重ねて置いてバランスを取ってみせた。僕はバランスを取り続ける彼を引き連れて、公園内にあるカフェスペースに向かった。

手に入れた木の棒でバランスを取るマルティン。なぜそんなことをするのかは分からない。
小綺麗な観光客向けのカフェの外には数人のハイカーたちがたむろしていた。どれも見た事ことがない顔だ。ここ最近、僕は全ての街には降りずに一気に距離を進めていたので、ハイカーたちを日々追い抜かし続けてきた。本来なら今日の朝のダンキンドーナツでもこのベテランズ・ウォー・メモリアル・タワーでも足を止めることはなかっただろう。マルティンによってハイキングペースが大きく乱されているのだ。
僕らはカフェでソーダを買って、ハイカーたちに混じった。彼らは僕よりも年配のハイカーで、やはり3ヶ月以上も歩いている汚いオーラを醸し出している。まさにこれぞスルーハイカーといった雰囲気だ。
いつものようにハイカーたちに挨拶をしてお互いの近況を簡単に報告し合う。そして、マルティンが先日僕に会った時ときのように「思い立ってろくな準備もせずにアパラチアン・トレイルに来た」と話しはじめた。僕はニヤニヤしながら彼らが驚く反応を待っていた。
しかし、彼らの反応は僕の予想に反したものだった。
「クレイジーだな。」
そう言ってただ呆れた表情をしたのだった。僕は彼の面白さが伝わってなかったのかと思って、彼が段ボールを背負って歩いていること、地図アプリの使い方をまだわかっていないことを話したが、彼らは呆れるばかりで最終的には怪訝な雰囲気になってその場を去ってしまった。
ちょっと気まずくなってマルティンの顔を覗き見したが、彼は全く気になっていないようで先ほど拾った棒に自分の名前を書き込んでいる。僕はこの嫌な感覚を少し前にも感じたことを思い出した。

真剣な面持ちで油性ペンで枝に名前を書いている。
遡ること1ヶ月ほど前、ちょうど街の教会でトレイルマジックが行われていて、そこに集まったハイカーの中にアパラチアン・トレイルをスルーハイクしようとしているトレイルランナーがいた。20リットルほどの小さなバックパックに軽量なランニング用ポールを持った彼は目立っていた。
「もしかして、君はランニングスタイルでアパラチアン・トレイルを踏破するつもりなのかい?」
僕はホットドックを食べながら話しかけた。
「そうなんだよ。普段からトレイルランニングしているしね。」
「かっこいいね。大体どれくらいで踏破するつもりなの?」
「最速記録を作りたい訳ではないから、そこまでシリアスじゃないのだけど、2ヶ月くらいだと思うよ。」
「僕の2倍以上の速さじゃないか。これはすごいな。」
「彼女のサポートのおかげもあるけどね。」
彼はホットドッグとソーダをたいらげると「お互い楽しもうな」と言って走り去っていった。アパラチアン・トレイルはアメリカ3大トレイルの中で最もトレイルランナーが力を発揮できるトレイルだ。というのも、補給ポイントが近いので、移動速度が速ければ速いほど運ぶ荷物が少なくなり、セクションによっては食料を全く持ち運ばなくてもよいときさえある。
しかし、これを達成するにはやはり強靭な肉体が必要なわけで、誰でもできるわけではない。
彼の後ろ姿を見送っていると、40代くらいのクラッシックな装備の男性ハイカーが僕の横で話しているのが聞こえた。
「ゆっくり歩かないとトレイルの楽しさは分からない。俺はあいつのスタイルが嫌いだ。」
以前から少し気になっていたが、アパラチアン・トレイルのスルーハイカーたちは絆とも呼べるような強い一体感を持ってハイキングしている。ほとんどのハイカーたちが今回が初めてのロング・ディスタンス・ハイキングで、色々な苦難を乗り越えながら3ヶ月間歩き続けてきたのだ。そしてトレイル・エンジェルや道中のホステルの人たちも、ハイカーを伝統としてもてなすので、コミュニティーの結束はどんどん強くなる。しかし、この枠組みを外れたハイカーを毛嫌いする傾向も少なからずあった。実際僕も嫌われる側のひとりであるのかもしれない、と思うことは時々ある。
なぜなら彼らハイカーたちの悩みに全く共感していないからだ。共に楽しむことはできたが、過去の経験と比べて圧倒的に不安要素の少ないアパラチアン・トレイルは挑戦的なものでは僕にはなかった。どうすればもっと楽しめるのかばかり考えていたので、伝統的なスタイルを重んじるハイカーからは変なやつとして区分されているに違いない。
だからこそ、「スルーハイカーっぽさ」から大きく逸脱したマルティンは僕にとって最高に面白い人物だった。彼が何を考えてるか全く分からないし、これからどんな失敗をするかも分からない。今回のトレイルで初めて大きな不確定要素をもたらす存在なのだ。それに彼には他人がつい手を貸したくなるような不思議な魅力も持ち合わせていた。

全く流れのない川で急に水浴びをするマルティン。意外にも清潔好きなのかもしれない。
マルティンとの別れ
僕はスケッチを終え、彼は新しいダンボールを手に入れてトレイルに戻った。今度は坂を延々と下っていく。僕にはひとつ不安なことがあった。
「なあ、マルティン。この後の天気ちゃんと見たかい?」
「見てないけど、どうしたの?」
「多分雨が降るぞ。」
彼の顔が曇った。本当に雨は降らないと信じていたらしい。
「どうしよう?」
「ちなみに雨を防ぐものって何か持ってるのか?」
「何も持っていない。」
「全く何も?」
「全く何も持ってないさ。」
これは困ったことになった。僕の1人用テントにふたりで寝れなくは無いが、ずぶ濡れの男が身を寄せ合って一夜過ごすのは避けたいし、シェルターに泊まってしまってもいいが、今後のことも考えて一応は雨対策をしたほうがいいように思えた。幸運なことにトレイルを下るとノースアダムズという街がありそこにはスーパーマーケットがある。僕らはそこで何かしら購入して簡易的なタープでも作ろうと考えた。
山を下った先のノースアダムズのスーパーマーケットは豊富な食材を取り揃えていたが、僕らが探していたタープの幕となるようなものは見当たらなかった。
困ったことになってしまったと心配している僕とは裏腹に、マルティンは楽しそうに店内を徘徊していた。
「これでなんとかなるかもしれない。」
マルティンが棚から何やら取り出す、それは食品を包むときに使うサランラップだった。
「これをハンモックに巻きつけるってこと?」
「正解! これで大丈夫だと思うんだ。」
「僕には無理だけど、君だったらきっとできるよ。信じてる。」
1ロールでどれ程までにハンモックを包む事ことができるのか分からない。しかし、ハンモックに入った状態で足から順に自分を包装していく彼の姿を見たくもある。何よりも、この店で雨をまともに防げるものが他に無いのだから、何を言っても仕方がないのもまた事実であった。

何か使えるものがないかスーパーマーケットを物色するマルティン。
次の街は少し離れているので2日分の食料を購入してトレイルに戻る。街からトレイルに戻るには郊外まで歩き、ハイウェイを越えるための歩道橋を渡る必要があった。その橋を渡ろうとした時ときにポツリポツリと小さな雨粒の跡がコンクリートの上にでき始めた。僕は急いでレインジャケットを着て軽量の日傘をさすが、マルティンは段ボールを頭上に掲げることしかできなかった。
雨足は次第に強くなり、数メートル先が見えないほどの大雨になった。僕らは急いで歩道橋の下に潜り込もうとしたが、大人ふたりが身を隠せるスペースなどなく、なす術なく雨に打たれ続けた。次第にマルティンのダンボールは水を含んで重く柔らかくなってきていた。もう、どうにもならないことは明白だった。
「スケッチ! もうだめだ! 僕は一旦街に戻るよ!」
雨粒が傘に当たってうるさいが、かろうじて聞き取ることができた。
「僕はそんなに今日は歩かないつもりだ。この雨も一時的なものだと思う! だから、今夜にでもまた会えるさ!」
「わかった! またすぐに会おう!」
マルティンが雨の中を走り去っていくのを見て、僕はもう彼はトレイルに戻ってこないかもしれないと感じた。
ひとりになった僕は豪雨の中、アパラチアン・トレイルに戻った。傘をさしていたが全身はすでにずぶ濡れになっている。2時間ほど経っても依然として雨は降り続けていた。時計を見ると15時くらいだが、僕はすでに歩くのが嫌になっていた。本日のハイキングはここで切り上げてしまうことにした。幸いトレイル脇にはテントを張れるスペースがある。
急いでテントを張り、濡れた服を脱いで裸で寝袋の中に入った。徐々に全身ずぶ濡れの不快感が薄れ、ゆっくりと眠りに落ちていた。
バシバシ! バシバシ! とテントを誰かが叩く音で目が覚めた。
「誰だい?」
「マルティンだ!」
僕は寝袋から上半身だけ出して、慌ててテントの外に這い出た。雨上がりの冷たい空気が頬を撫でる。そこに立っている彼を見て、数時間前に別れたばかりなのに懐かしさが込み上げてきた。
「ひさしぶり、マルティン。」
「ひさしぶり、スケッチ。」
「ところで、街まで戻っていたのかい?」
「いや、実はすぐ近くの民家に避難してたんだよ。」
「どうやって?」
「あのあと、叫びながら走ってたんだ。それを見て心配した老人が家に招待してくれて、ディナーもご馳走してくれたんだ。」
「なんだって! それだったら、僕も君と一緒に行けばよかった!」
しかし、それはおそらくマルティンひとりだったからこそ可能だったのだろう。
「そして、これを見てくれよ!」
彼は嬉々として背中をこちらに見せた。
「もしかしてだけど、バックパックが新しくなってないか?」
「そうなのさ! 彼の息子が買ったけど使ってないバックパックを持っていたから、それを譲ってくたんだ。僕のバックパックがあまりにもボロボロだったからだろうね!」

新しいバックパックを手に入れたマルティンはエネルギーに満ち溢れていた。
彼の新しいバックパックは深い緑色で50リットルほどありそうだ、そのバックパックにはしっかりと新しいロール状の段ボールが固定されいた。
きっと老人たちもマルティンを助けずにはいられなかったのだろう。そして喜ぶ彼を見て、愉快で幸せな心持ちになったに違いない。
もしかしたら、今回の旅は彼が刺激として必要なのかもしれない。早く身支度して一緒に歩き始めないと、と思った矢先、彼は「じゃあまた後で会おう!」と言って立ち去ろうとした。僕が引き止めようとした瞬間、彼のブーツがペグを蹴り抜き、僕のテントは倒壊して目の前がシルナイロンのグレー一色になる。彼はそのことには気づかなかったようで、遠ざかる足音だけが聞こえた。
僕は服を探すのが面倒臭くなり全裸で外に出てテントを建て直し、すぐに中へ戻る。そのときには本日のハイキングの気力は消え去ってしまっていた。また、明日にでもたくさん歩いて追いつけばいいさ。そう考えていた。
しかし、そのチャンスは2度と訪れなかった。
翌日、僕は知らないうちにマルティンを追い抜かしてしまい、それを知らずにどんどんと距離を伸ばしてしまったのだ。
トレイルマジックにて

トレイルマジックを楽しむハイカーたち。こんな日はもう歩けない。
マルティンと別れてから1週間が経ち、僕はバーモント州のグリーン・マウンテン国有林のダートロードでトレイルマジックに遭遇していた。トレイルマジックをしている男性はキャンピング用のテーブルとチェアを並べ、ハイカーたちにホットドックやスナック、そして大量のビールを振る舞っている。その脇に停めてあるピックアップトラックの荷台には発電機が積まれていて、ハイカーたちはここぞとばかりにモバイルバッテリーを充電していた。
トレイルマジックをしている男性のキャップにはガムテープが貼られていて、なぜかそこには大量の蠅や蜂の死骸がくっついていた。

僕より先に男性ふたり、女性ひとりがいて、彼らはすでに酔っ払っていて、もはや今日のハイキングは放棄しているように見えた。
僕はその光景だけで楽しくなって、彼らに混じりビールを飲んだ。3人ともソロハイカーで一50代と30代の男性、女性は僕らと逆の南下ルートを歩いている20代女性だった。南下するハイカーは北上するハイカーよりスタートが遅いのが通例だ。そろそろ、2方向のハイカーが交差するタイミングなのかもしれない。
飲み始めてから1時間ほど経った頃に、10代の若いハイカーのグループがやってきた。男性がビールを勧めると彼らはどうするか相談していた。彼らはとても急いでいるようで、今日の目標としている距離のことを気にしていたが、結局は誘惑に負けて腰をおろす。

トレイルマジックの貼り紙。これを見てハイカーたちが集まってきていた。
ロング・ディスタンス・トレイルではトレイルランナーの他に高速でハイキングをする人たちがいて、それが彼らのような大学生だ。大学生は3ヶ月の夏休み中に全行程を歩かなければならないので1日に30マイル以上も歩く。
その時、スマートフォンがメッセージを受信して振動した。確認してみると、それはなんとあの懐かしいマルティンからだった。実は数日前に彼へメッセージを送っていたが、ずっと返信がなかったのだ。
「スケッチ元気かい? 返信が遅れてごめんよ。今、ボストンの空港に向かっていて、もうスペインに帰ることにしたよ。 あのあと、雨がずっと降っていて、とてもじゃないけどハイキングできなかったよ! スペインに来るときはいつでも連絡してくれ!」
確かに彼と別れてからずっと天気が悪かった。きっと何度も雨の中で騒ぎ続け、色んなハイカーに迷惑をかけたのだろう。そう考えると面白くて仕方なかった。そして、無事だったことに安堵した。
そして、その状態で少なくともひとつの小さなセクション、だいたい3日ほどをハイキングしたのだろうから、それはそれで凄いことのように思えた。
彼との出会いは僕にとってどこかノスタルジーを感じさせるものだった。きっと2015年にパシフィック・クレスト・トレイルを歩くためにはじめてカリフォルニア州に降り立ったときの無知な自分を思い起こさせたからだろう。
あのときは何も知らないままアメリカにやって来て、ハイカーたちにスーパーマーケットでトレイルフードの補給の仕方までも教えてもらっていた。それから、歩きに歩き、もう3大トレイル踏破まで真直というところまで来ている。そんなときに出会った無知なスペインの青年は、僕の中で少し退屈に感じはじめていたアパラチアン・トレイルの素晴らしい刺激になってくれたのだった。
今日はマルティンとハイキングした初日のように珍しく快晴だ。ハイカーたちはそれだけで気持ちよさそうにしている。このトレイルマジックの雰囲気はとてもラフで心地良い。
マルティンもこの場にいたらきっと楽しかったのにな、と思いながら、僕は新しいビールのプルタブをおこした。
#7に続く