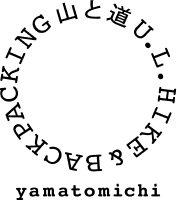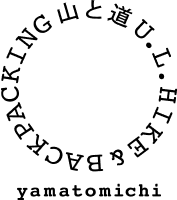アメリカ東部のアパラチアン山脈沿いに3500kmに渡って伸びるアパラチアン・トレイル(AT)は、「トリプルクラウン」と呼ばれるアメリカ3大ロングトレイルのひとつにして最も長い歴史を持ち、また最も多くの人が歩く、まさに「ロングトレイルの中のロングトレイル」とも呼べる存在です。
2019年、イラストレーターにしてロングディスタンスハイカーのトレイルネーム”Sketch”こと河戸良佑さんが、彼にとって「トリプルクラウン」最後の1本となるATに挑みました。この連載では、5ヵ月に及んだその長大な旅を通じて、彼の覗いたアメリカのロングトレイルのリアルを活写していきます。
出会うハイカーたちと安酒を酌み交わすうちに、ようやくATのノリにも慣れてきたSketch。今回はそんな彼の本領発揮ともいえるパーティのエピソード、毎年5月にヴァージニア州ダマスカスで行われるイベント「トレイルデイズ」に参加した顛末を綴ってくれています。
長いトレイル生活の反動か、「もっと狂ってしまわなければならない」という衝動に突き動かされ、例によって酒とゲロにまみれるSketchですが、さすがの彼にもふと我に帰る瞬間があったようで…。

Appalachian Trail
アメリカ東部のアパラチアン山脈に沿ってジョージア州からメイン州まで14州をまたいで伸びる約3,500kmの超ロングトレイル。開拓時代の旧跡も多く巡るルートはアメリカのルーツに触れる旅としての側面もあり、毎年数千人が踏破を試みる。
もっと馬鹿騒ぎしたいんだ!
アメリカで長距離ハイキングしていると、狂ったように騒いだ方が良いと思う時がある。いや、そうせねばならない時がある。
過去にPCTのカルフォルニア州ベルデンのサンセットフェスティバル。CDTのニューメキシコ州パイタウンのハロウィンパーティー。あれは忘れもしない馬鹿騒ぎだった。
そして今回のアパラチアン・トレイルでもついにその時が訪れた。「トレイル・デイズ」だ。

2017年のPCT。カルフォルニア州ベルデンでサンセットフェスティバルがはじまるとハイカーたちは集結を始めた。彼らとは3ヶ月ぶり再会した。

2018年CDT。パイタウンでのハロウィンパーティー。この時はにこやかであったが、我々はこの夜に老人たちにテキーラを飲まされ続けて気絶した。
2019年5月17日、アパラチアン・トレイル上のヴァージニア州ダマスカスの人口800人ほどの小さな田舎町に、2万人以上のハイカー達が馬鹿騒ぎをするために集結していた。毎年5月にこの地で開催される「トレイル・デイズ」は、ロング・ディスタンス・トレイル関連のハイカーやトレイルエンジェルなどが集結するアメリカ国内最大のハイキングイベントだ。
アパラチアン・トレイルで「トレイル・デイズ」に参加することは、ハイカーたちの大きな目標のひとつになっていて、ダマスカスまでわざわざヒッチハイクでやってくるハイカーも少なくない。
僕はちょうどトレイル・デイズの初日に徒歩でダマスカスに到達したが、これは全くの偶然だった。

トレイル・デイズ会場入り口。到着した時間が早かったため、まだなにも催し物は始まっていなかった。
街の中央に位置する大きな公園がトレイル・デイズのメイン会場になっていて、バンドが演奏するステージやアウトドアブランドの出店スペースとなっている。そして公園内の野球場横の広場とその裏の森のキャンプ地で、ほとんどのハイカーはテント泊をしているようだ。
公園内だけでなく、近くの教会や個人宅でも無料の食事が提供が行われていて、小さな町全体あげての大イベントになっていた。
「やあ! スケッチ! 久しぶりだな!」
広場にテントを設営したのちに、さまざまなアウトドアブランドのブースを眺めながら、ふらふらと歩いていると声をかけられた。そこにいたのは数週間前にトレイル上で会ったハイカーたちだ。彼らはダマスカスより少し離れた街からトレイルエンジェルの車に乗って会場にやってきたという。
少し会話をして別れると、またすぐに「スケッチ! 久しぶりだな!」と違うハイカーから声をかけられた。彼も以前にトレイル上で出会っていた。「もしかして」と思ってあたりを見渡すと、なるほど知った顔のハイカーがあちらにもこちらにも歩いている。

久しぶりに出会ったハイカーグループ。どう見てもうかれている。
ハイカーたちを眺めると、どいつもこいつも浮かれていて、僕にはその気持ちがよく分かった。アパラチアン・トレイルはここまでの道中さほど愉快ではなかったからだ。ハイカーたちは蒸し暑い不快な気候や気まぐれに降る雨に耐えながら歩き続けてきた。訪れた街もそれほど印象的ではなく、トレイルから見える景色は木々ばかりで退屈だった。
それでもここまで歩いてこれたのは、ハイカーやトレイル・エンジェルとの素晴らしい出会いがあったからだ。言うなれば50年の歴史を持つアパラチアン・トレイルの深いハイキング文化が僕たちを支え続けてきた。

無料で食事が提供されている教会に集まるハイカーたち。

ハイカーたちへ手作りの帽子を配るエンジェルたち。アパラチアン・トレイルの優しさを感じる。
そして、その全てが今、このダマスカスに集結しようとしているように感じ、次々と現れる懐かしい顔につられて僕も次第に高揚してきていた。そして確信した。「今夜はハメを外さねければならない」と。
どいつもこいつも狂ったよう
まず僕は近くにいるハイカーたちと1ドル均一ショップの『ジェネラルダラー』に駆け込んで安物のビールとワインを買い込んだ。もはや出店しているアウトドアブランドに1ドルも落とす気はなく、今夜いかに騒ぐかしか頭になかった。
『ジェネラルダラー』の前にはハイカーがたむろしていて、みんな考えることは同じなようだ。僕らは会場でとにかく酒を飲み続け、そしてなくなるとまた店に戻る。
途中、トレイルエンジェル宅の炊き出しに並んでいたはずなのに、何故かパスタを茹でる手伝いをしていた。それくらい僕は泥酔していたが、まだまだ飲み足りなかった。

ジェネルダラーで酒を求めるハイカーたち。アメリカでは屋外での飲酒は違法なので店の前では誰も飲まない。

ショーという名前のトレイルエンジェルの家で、気がついたら炊き出しの手伝いをしていた。
すれ違ったATハイカーのゴッドスピードはどこかで拾ったプレートを腕につけて僕に自慢してきた。それが可愛くて強くハグをする。その後ろにいたインド人ハイカーは彼の本名の発音が難しすぎて、それが面白くてハグをした。
もうどんなことが起きても面白かった。もう会えないと思っていたカナダ人女性ハイカーのマンゴーは、膝が痛くなりがちのサムとキスをしていたので、その時ばかりは邪魔にならないように静かに通り過ぎた。

プレートを腕に装備してトレイル・デイズを楽しむゴッドスピード。ちなみに彼の歩くスピードは遅い。
気がつくと日は暮れていて、僕は数え切れないほど会場を周回して、数え切れない人とハグをして、数え切れないほどの缶ビールを空にした。意識はずっと朦朧としていて、僕の脳は動くのをやめようと必死だ。
それでも「もっと狂ってしまわなければならない」という衝動と、「この機を逃すとアメリカの思い出を欠いてしまう」というケチくさい気持ちが僕を突き動かしていた。

夜になると周囲は真っ暗で、テントの明かりを頼りに森を彷徨った。
夜になっても僕は空腹のまま彷徨った。森の中からふわりとトマトの香りがする。それにつられてテントの中に入ると髭の長いヒッピー達がいた。そのうちのひとりが「お腹すいているかい?」と尋ねるので、僕はヘラヘラ笑いながら「もうペコペコだよ」と答えると、彼らはミートスパゲティを皿いっぱいによそって僕によこした。それを持って椅子に座り周囲を見渡すと、青白い顔をしたハイカーたちがボソボソとパスタを食べていた。
「なあ、いい感じかい?」
隣の男が話しかけてきた。彼の顔を見ようとするが頭が重くて、視線を向けることができない。
「完全に、完全にいい感じだ。」
僕はミートソースを見ながら、やっとのことで声を搾り出す。
「そりゃよかったな。『イエローデリ』に感謝だ!」
「『イエローデリ』? 何なんだそれは?」
「このヒッピーコミューンのことさ。世界中にあるんだぜ。」
「知らなかったなそれは。僕は……僕はただパスタにつられてきただけなんだ。」
「そんなのみんな同じだろ?」
「そうだな。ここにいるみんな同じなんだな。」

イエローデリのテント内。写真を撮った記憶はもちろんない。
髭についたミートソースを手でぬぐって立ち上がり、ふらふらと森の中を歩いた。遠くで響く低音のビートが空気を揺らしているのを感じた。僕は音の糸を掴みながら頼りない足取りでゆらりゆらりと森の中を進む。
歩いていると誰かにハグをされてボトルを手渡された。その中のウィスキーを喉に流し込み、またふらふらと歩く。僕は音の震源地すぐ近くまで来ていた。重い頭を持ち上げ、細い目であたりを見る。
300人を超えるハイカーたちがそこにはいて、どいつもこいつも狂ったように騒いでいた。人だかりの中心では、ポリバケツやウォーターボトルや鍋の即席ドラムをハイカーたちが叩いてリズムを刻んでいた。僕はもう何も考えられなくなっていて、ただただリズムに合わせて体を揺らす。
ドン、ドッドン、タカタカ、ドン、ドドドドン、タッタ、ドンドンドンドンドンドン……
何か特別な曲を演奏をしているわけではない。ただ低音が刻む単調で原始的なビートのループがハイカーたちの熱を渦のように絡めとり、中央で炎となって夜空へ巻き上げていた。

ハイカートラッシュドラミング。ヒッピー要素の薄いアパラチアン・トレイルだが、この瞬間は完全に違っていた。
僕は完全にトランス状態になっていて、自我を手放しては引き戻して楽しんでいた。どれくらいの時間、そうしていたか分からない。急に甲高い犬の叫び声が音の洪水の中から僕の耳に飛び込んできた。見ると騒ぎ過ぎたハイカーが近くにいた犬を誤って蹴ってしまったようだ。
「おお、本当にごめんよ、ごめんよ!」
蹴った彼は飼い主に抱き上げられた犬に謝っていて、それを見ていると次第に興が醒めてきた。僕はいよいよテントに戻って寝ることにした。もう時刻は午前4時を過ぎている。帰る途中で気分が悪くなってミートパスタを全部吐き、汚れた口をビールで洗ったところで記憶が途切れた。
ハイカーに埋め尽くされた広場
テントの中で目を覚ますと猛烈に喉が渇いていた。近くに転がっていた気の抜けたコーラを飲み、テントから這い出る。もう日は高く昇り、会場には人が溢れていていた。腹が減っていたので教会へ行き、無料で提供されていたマフィンとコーヒーを飲む。
二日酔いからくる倦怠感が体から抜けるのをのんびりと待っていると、ゴッドスピードが入ってきた。彼はスターウォーズの悪役のような黒いローブを纏い、アホっぽい派手なサングラスをつけていた。
「ヘイ! ゴッドスピード! なんでそんな格好してるんだよ?」
彼はサングラスを外し、こちらに近寄って来て、向かいの席に座った。
「パレードに参加するんだよ。」
「パレード?」

蒸し暑いテントの中で目を覚ました。すぐ横で吐いていたので白い段ボールで隠している。

途中で僕と同じトレイルネーム”SKETCH”に出会った。彼は過去にスルーハイクしたハイカーで、今は画家をしている。スケッチブックにサインをもらう。
「知らないのかよ? ハイカーがみんなでメインストリートを行進するんだ。現役も過去のATハイカーたちも参加するんだぜ。つまり、お前も参加しろってことよ。」
「つまり、僕も参加しなくてはならないってことか。」
「そう言うことさ。ところでフライドチキンはどこ?」
「フライドチキンはもう無い。」
「クソッタレが……まあいいさ。じゃあ、またな。」
彼が去るのを見届けて、iPhoneでトレイル・デイズの日程を調べる。すると確かにハイカー・パレードという催しが午後の2時からあった。
僕は教会を後にすると、昨日のトレイルエンジェル宅の炊き出しボランティアをした際にもらった「NO PAIN, NO RAIN, NO MAINE(MAINEはアパラチアン・トレイル最後の州の名前)」とプリントされたTシャツに着替え、広場でREIのワークショップでサングラスを作って装着し、次に年配の方達が手編みした麻の帽子をもらって被った。ゴッドスピードのコスプレには劣るが、間に合わせにしては次第点といった感じにはなっただろう。

可能な限りパレード感を出そうとしたが、即席の衣装ではこれが限界だった。
そうこうしているうちにパレードが始まる時間が近づいたので広場へ向かうと、僕は驚いた。パレードに参加するハイカーたちで埋め尽くされていたのだ。パレードが始まり、ダマスカスのメインロードを歩き始めると、どれだけ多くのハイカーが集まったかさらによくわかった。
約800mのダマスカスのメインストリートの端から端までハイカーでびっしりと埋まっていたからだ。

ダマスカスのメインストリートを練り歩くハイカーたち。
皆が手を振りながら歓声をあげていた。路肩から子供たちが水鉄砲で、大人はホースで我々に水をかける。パレードの中には、やはりチラホラとこれまでトレイル上で顔を合わせたハイカーたちを見かけた。嬉々とした彼らの表情を眺めながら、僕はツーリストのようにパラパラと写真を撮って歩いた。
各年にハイキングしたハイカーがブロックごとに分かれ町を行進している様はまるでATハイカーの同窓会のようであり、50年続くアパラチアン・トレイルの歴史の系譜が今後も途切れないことを誇示しているようにも思えた。パレードを終えたハイカーたちは広場に戻り、皆とても高揚していて、ハグをして笑い合っている。
そんな時、大きな歓声が上がり、一体、何事だろうかと向かってみると、某有名アウトドアブランドのブースの前にものすごい人だかりができていた。
よく見るとそのブースではスタッフが群衆に向けて小さい何かを放り投げていた。そのひとつが足元に落ちてきたので拾い上げてみると、それはスプーンとフォークが一体になったプラスチック製品で、彼らはそれとは別にロゴ入りのプレートやカップなども投げていた。先ほどまでアパラチアン・トレイルの歴史に触れていたのに、今度は急に神社の祭りの餅投げに出くわしたようで奇妙な気持ちになった。

さまざまなブランドのブースが並ぶ。B級品が安く売られたり、ギアのリペアサービスがあったりとスルーハイカーには嬉しい。

僕が使っている地図アプリのGUTHOOK GUIDESブース。
別のブランドのブースでは、ひとりのスタッフが壇上でマイクを持って叫んでいた。
「今から1000ドルぶんの商品をこの中のラッキーなやつにプレゼントだ!」
どうやら、事前に配っていたクジの当選者を発表しているようで、ブースの前はハイカーたちでごった返していた。
「スーパー宣伝的だな、こりゃ。」
僕の横にいたコインズがボソリと言う。彼は袖を破り取られたヘンテコな中華風のシャツを着ていた。
「僕らには縁のない世界だ。トレイル・デイズはこれにて終了って感じかな。」
「違いない。あとはテントの中でゴロゴロしておくとするか。じゃあスケッチまたな。」
そう言って彼は雑踏の中に消えていった。
「A19383のくじを持っている奴はいるかい? 君に1000ドルの商品券だ! え? いないって? じゃあ、A23994は誰か持っていないか? これもいないって? どうなってるんだよ。じゃあ次の番号はA1235……」
馬鹿騒ぎよりも必要なもの
トレイル・デイズの2日後、僕はダマスカス郊外の静かな森の小川でひとりの初老男性と釣りをしていた。
彼の名前はエド。2017年にハイキングしたコンチネンタル・ディバイド・トレイルで一緒に過ごしたシュウェップスというハイカーの父親だった。シュウェップスも僕と同様に、今年(2019年)アパラチアン・トレイルを2度目のスルーハイクしていて、彼はここから歩いて5分ほどの自宅でBBQの準備をしていた。
トラウトロッドでルアーを投げていたが、うんともすんとも反応がなかった。とりあえず食材を確保するために、釣ることを優先して針にミミズをつけて放り投げていた。
退役軍人で立派な体躯のエドは、白髪混じりの長い顎髭を蓄えていた。彼はかなりのガンマニアだった為、昨日はからライフルからマシンガン、そしてハンドガンの練習をさせられ続けていたが、僕には射撃の才がなかったし、思ったほど楽しい行為ではなかったので苦痛ではあったが、それでも典型的なタフなアメリカ人の父親という雰囲気は、どこか頼もしく心地良いものだなと感じていた。

実はこの川はエドの私有地なのでライセンス無しで魚が釣り放題だ。

シュウェップスがATで出会ったパートナーもエドの銃レッスンを受けさせられていた。彼女は後日「銃より花が好き」と言っていた。
竿先にグッグッと強いアタリを感じる。慌てて竿を立てて合わせると、竿は弧を描いて大きくしなりリールのドラグがジジッジーと音を鳴らしながらラインを送り出す。かなり細いラインを使用していたので、無理に引き寄せると切れてしまう可能性があった。僕はそっと竿を立ててラインがが緩んで魚から針が外れないようテンションを保ち、魚が疲れるのを待つ。
慣れぬ様子で格闘している姿を、少し離れていたところで釣りをしていたエドが見つけ慌てて駆け寄ってきた。
「よーし、いい感じだ。無理するなよ。ラインがすぐ切れてしまうからな。」
「このトラウトはなかなか大きい気がするよ。」
「これは絶対にキャッチしよう。俺たちの晩飯の為に。」
魚の動きが少し鈍くなってきた。ラインが緩まないように竿を下げると同時に巻き取り、そしてまたゆっくりと竿を立てて、魚を川底から引き上げる。
少しづつ慎重に続けていると、水中で大きな銀色に体が一瞬ギラリと光って見えた。なかなかの大きさだ。
「ゆっくりだ。ゆっくりだぞ。」
エドはネットを構えていて、いつでも魚を掬い取れる用意をしていた。するとふわりと40センチ程のレインボートラウトが水面に浮上してきた。僕は緊張して腕に力が入る。
「スケッチ! 焦るなよ。ゆっくりだぞ!」
ゆっくりと竿をコントロールしてトラウトを岸に寄せるが、ネットに誘導する直前でトラウトは暴れて川の底へ走る。このやりとりを何度か繰り返す。最後は動きが鈍くなったトラウトをエドが川に入ってランディングした。
網の中に収まったトラウトはたっぷりと肥えて、銀色の体に黒い斑点を飾り、薄い紅色の線が綺麗に体に入っていた。
「スケッチ、よくやった!」
「いや、エドのおかけさ! ありがとう!」
僕らは強くハイタッチをした。今日の釣りはこれで終了だ。あとはシュウェップスに調理をしてもらうだけだ。今夜はトラウトを食べながら、ビールを飲んで彼らとの時間を楽しもうではないか。

でっぷりと太ったトラウト。初心者の僕にしてはなかなか大物である。

僕はさらに晩飯を追加して大満足だった。この楽しさが、今後の新しいハイキングのヒントになった気がした。

BBQの準備をするシュウェップス。トレイルでも大切なのは人との繋がりだ。

2017年にCDTをハイキングしていたシュウェップス。車があまりに来ないので、寝転がってヒッチハイクしている。
僕がダマスカスに来て6日が経つ。トレイル・デイズの直後は少し焦燥感のような気持ちがあり落ち着かなかったが、今はやっといつも通りのスケッチに戻った気分だった。
帰り支度をしているエドを見ながら、馬鹿騒ぎなんかよりもこのような小さな交流をたくさん経験することの方が、今の僕には必要だと思った。明日にはアパラチアン・トレイルに戻ろう。そう心に決めた。
【#5に続く】